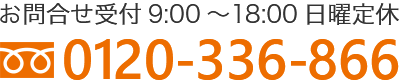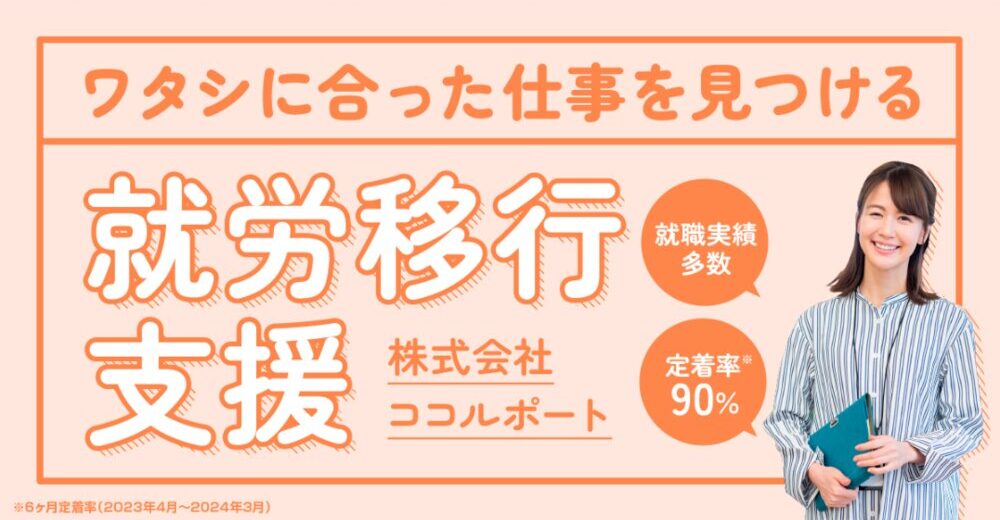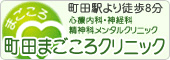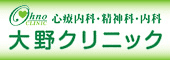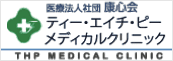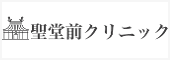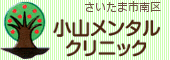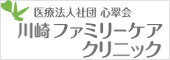- ココルポート(就労移行支援・定着支援/自立訓練/計画相談) HOME
- お役立ち情報
- 感音性難聴とは? 原因・症状から治療、仕事の悩みと対策まで解説
感音性難聴とは? 原因・症状から治療、仕事の悩みと対策まで解説
公開日:2025/08/18
更新日:2025/08/18

「感音性難聴」と聞いて、どのような印象を持ちますか? 自分や家族が診断を受けて不安になっている方もいるかもしれません。感音性難聴は、音が「聞こえる」だけではなく「理解する」力にも影響を及ぼす難聴の一つで、日常生活や仕事にさまざまな問題を引き起こすことがあります。
本記事では、感音性難聴の原因や症状、治療法について基礎から分かりやすく解説するとともに、仕事や暮らしの中でできる工夫、公的な支援制度についても解説します。
目次
感音性難聴とは

感音性難聴は、耳の奥にある内耳(蝸牛)から聴神経、さらには脳の聴覚中枢に至るまでの「音を感じ取る経路」に障がいが生じることで発症する難聴です。音が歪んだり、言葉の聞き分けが難しくなったりします。
主な原因は内耳の機能不全ですが、より奥にある聴神経や脳の働きに問題がある場合もあり、かつては「神経性難聴」とも呼ばれていました。
人が音を聞き取る仕組みは、外耳・中耳・内耳といった複数の器官が連携することで成り立っています。音の振動はまず耳介(じかい)で集められ、外耳道を通って鼓膜に伝わります。鼓膜の振動は中耳の耳小骨(じしょうこつ)で増幅され、やがて内耳の蝸牛(かぎゅう)に届きます。蝸牛内では、内耳液の振動がコルチ器を通じて電気信号に変換され、聴神経から脳へと送られ、音として認識できる仕組みです。
感音性難聴は、音そのものが届いていても「うまく感じ取れない」状態です。同じく、聴覚に異常が起きる病気に伝音性難聴があります。伝音性難聴は外耳や中耳に原因があり、比較的治療による改善が見込める場合が多いのに対し、感音性難聴は内耳や神経などの構造に由来するため、一般的に回復が難しいとされています。
ただし、補聴器や人工内耳など、適切な対処や支援によって、生活の質の維持・向上を目指すことは可能です。
感音性難聴の主な症状
感音性難聴の症状の現れ方には個人差があり、片耳のみのケースと両耳のケースがあります。また進行の速度や影響の程度もさまざまです。
具体的な症状の例は下記の通りです。
- ・単純に音が小さく聞こえるだけではなく、音が割れたり響いたりして聞こえる
- ・言葉の聞き間違いが多い(特に子音や高音域)
- ・早口や小声での会話、騒がしい場所での聞き取りが困難
- ・テレビの音量が大きくなる、インターホンや電話の音が聞こえにくい
- ・耳鳴り(キーン、ジーなど)を伴うことがある
- ・めまいを伴うことがある(メニエール病など特定の場合)
聴力レベルの程度によっても症状は異なります。軽度難聴(25〜39dB)では小さな声や雑音下での聞き間違いが主ですが、中等度難聴(40〜69dB)になると通常の会話でも支障を感じるようになります。
さらに、高度難聴(70〜89dB)では補聴器を使わないと会話が成立しにくくなり、重度難聴(90dB以上)になると補聴器でも十分に音が届かないため、人工内耳の装用が検討されることもあります。
症状に心当たりがある場合は、自己判断で放置せず、耳鼻咽喉科などで診察を受けましょう。
感音性難聴の主な原因
感音性難聴は、内耳や聴神経、あるいは脳の聴覚中枢に何らかの障がいが生じることで起こる難聴です。その原因は一つではなく、さまざまな要因が関与しており、大きく「先天性」と「後天性」に分けられます。感音性難聴の主な原因について詳しく見ていきましょう。
先天性の原因
生まれつきの感音性難聴の原因は、遺伝的な要因や胎児期・出生時のトラブルなどです。また妊娠中に母体が風疹やサイトメガロウイルスに感染すると、胎児の内耳の発達に影響を及ぼすことがあります。
さらに、分娩時の低酸素状態や重度の黄疸などによって脳や聴覚神経が損傷を受けることも原因の一つです。
後天性の原因
生後に発症する後天性の感音性難聴には、生活習慣や疾患、環境要因が関係しています。種類とそれぞれの原因、特徴は下記の通りです。
- ・加齢性難聴(原因の多くを占める、徐々に進行)
- ・騒音性難聴(強大な音への曝露、長時間騒音下での作業)
- ・突発性難聴(原因不明で突然発症、早期治療が重要)
- ・メニエール病(内リンパ水腫によるめまい、耳鳴り、難聴)
- ・薬剤性難聴(特定の抗生物質や利尿剤、抗がん剤などの副作用)
- ・聴神経腫瘍(良性腫瘍だが聴神経を圧迫)
- ・頭部外傷や中耳炎からの波及
- ・その他(ウイルス感染(おたふくかぜ、はしか)など)
- ・自己免疫疾患、糖尿病などの生活習慣病
このように感音性難聴の原因は多岐にわたり、特定が難しいケースも少なくありません。
感音性難聴の検査・診断

感音性難聴が疑われる場合、正確な診断を受けるためには、耳鼻咽喉科での専門的な検査が不可欠です。難聴の種類や程度、原因を明確にすることで、適切な治療方針や補聴器などの支援機器の選定が可能になります。
次のような方法で得た情報を基に診断されます。
- ・問診(症状、既往歴、家族歴、生活習慣、職業歴などを確認)
- ・視診(耳鏡や内視鏡で外耳道や鼓膜の状態を確認)
- ・純音聴力検査(聞こえる最小の音の大きさを周波数別に測定、気導・骨導の両方を測定し伝音難聴との鑑別)
- ・語音聴力検査(言葉の聞き取り能力を測定)
- ・ティンパノメトリー(鼓膜の動きや中耳の状態を調べる)
- ・耳音響放射検査(OAE)(内耳(特に外有毛細胞)の機能を調べる)
- ・聴性脳幹反応(ABR)、聴性定常反応(ASSR)(聴神経から脳幹までの反応を調べる、乳幼児や意識のない患者にも可能)
- ・画像検査(CT、MRI)(聴神経腫瘍や内耳奇形などが疑われる場合)
最終的には、複数の検査結果を総合的に判断し、難聴の種類・程度・原因を特定します。
感音性難聴の治療法と向き合い方
感音性難聴は、一般的に「完治が難しい難聴」とされていますが、原因や発症時期によっては、早期の対応によって回復が期待できるケースもあります。また完全に治せなくても、症状の進行を抑えたり、聞こえを補ったりすることで日常生活の不便を軽減し、生活の質(QOL)を保つための選択肢は多く存在します。ここでは、感音性難聴の治療法や対処法、長期的な向き合い方について解説します。
薬物療法
感音性難聴のうち、突発性難聴など急性のケースでは、薬物療法による回復が期待できます。使用する薬は、炎症や内耳のむくみを抑えるためのステロイド剤や、血流を改善する血管拡張剤、内耳の代謝を促すビタミン剤・代謝賦活剤などです。ただし、効果は発症からの時間や病態によって異なるため、早期受診が重要です。
一方、めまいや耳鳴りを伴うメニエール病が原因である場合には、内耳の水分バランスを整える利尿剤や、めまいを抑える抗めまい薬、補助的にステロイド剤などが使用されることもあります。
補聴器の活用
薬物による改善が見込めない場合、一般的な対応策が補聴器の使用です。補聴器は単に音を大きくするだけではなく、会話を明瞭にする周波数調整など、さまざまな機能が備わっています。形状は耳かけ型、耳あな型、ポケット型など複数のタイプがあり、聞こえの程度や耳の形、ライフスタイルに合わせて選択することが重要です。
購入前に試聴や装用体験ができる施設も多く、早期に装用を始めることで脳の聞き取り能力の低下を防ぐ効果も期待されます。
人工内耳
補聴器でも十分な効果が得られない高度〜重度の感音性難聴に対しては、人工内耳という選択肢もあります。これは、内耳に電極を埋め込み、音の情報を直接聴神経に伝える医療機器で、手術によって装着します。
手術後には音に慣れるための聴覚リハビリテーションが必要で、医療機関と連携して長期的に使用していくことが前提です。
人工内耳は全ての人に適応されるわけではなく、聴力の残存状況や生活環境、本人の希望などを総合的に判断して適応が決定されます。
その他の治療法・アプローチ
原因となっている疾患が明確な場合には、その治療を優先します。例えば、聴神経腫瘍が原因であれば手術による摘出が検討されることがあります。また、騒音曝露やストレス、不規則な生活習慣が悪化因子となるため、日常的な生活の見直しも重要です。
禁煙、騒音を避ける工夫、ストレス管理、バランスのとれた食事、適度な運動などは、耳の健康を守る上で基本的な対策といえます。さらに、耳鳴りに悩む方には、TRT(耳鳴り再訓練療法)などの音響療法も行います。
症状との上手な付き合い方
感音性難聴は、ただ治すことを目的とするだけではなく、今の聴力を生かしながら生活の質を維持・向上させるという視点も大切です。その一つが聴覚リハビリテーションです。読話(口の動きを読み取る)、聴能訓練(補聴器使用後のトレーニング)などを通じて、聴こえにくさを補う技術を身に付けられます。
また周囲の人の理解と協力も重要です。話しかける際に正面から話す、ゆっくりとした口調で話す、背景音を減らすなどの方法があります。さらに、同じ悩みを持つ人との交流(ピアサポート)も、心理的な支えとして有効です。
感音性難聴は、完治を目指すだけではなく「今できることを最大限に生かす」姿勢が、長期的な生活の安定につながります。
感音性難聴と仕事|困りごとと職場でできる工夫
感音性難の方にとって、仕事の場面では「聞こえにくさ」そのものが障がいとなることがあります。特に音声による情報伝達が中心となる職場環境では、誤解やすれ違いが生じやすく、業務上のストレスや不安が積み重なってしまうことも少なくありません。
しかし、聞こえにくさがあることを前提に、適切な工夫や配慮を行うことで、多くの困難は軽減または解消が可能です。
ここでは、感音性難聴のある方が仕事で直面しやすい課題と、その対処法について詳しく見ていきます。
仕事で起こりやすい困りごと
感音性難聴があると、業務の中で大きな影響を受けやすいのが「音声によるやり取り」です。会議や打ち合わせでは複数人が同時に発言することが多く、聞き取りが追いつかない、発言者の位置によって内容が聞き取りにくいといった状況が生じます。
また電話応対では相手の声が不明瞭になりがちで、聞き取りミスにつながるリスクが高まります。こうした状況が続くと、周囲とのコミュニケーションが減り、孤立感や自己否定感を抱きやすくなります。
加えて、音に常に集中していることによる疲労やストレス、騒音の多い作業環境での過度な緊張感、理解されないかもしれないという不安が精神的な負担になることもあるでしょう。
個人でできる工夫・対策
感音性難聴があるからといって、必ずしも仕事の継続が難しくなるわけではありません。まずは自分自身の工夫によって、情報の取りこぼしを減らすことが重要です。聞き取れなかった場面では遠慮せず聞き返す姿勢を持ち、指示や内容をすぐにメモする習慣を付けることで、記憶を補完しやすくなります。
また補聴器や集音器などの補助機器を積極的に活用することも、聞き取りの改善につながります。会話の聞きやすい位置に座るよう配慮を依頼したり、できるだけ静かな環境で作業を行えるよう調整したりといった工夫も効果的です。
業務連絡や相談は、メールやチャット、メモなど視覚的な手段を積極的に取り入れることで、聞き漏れや誤解を減らせます。加えて特に疲労や睡眠不足が聞こえの感度に影響を与えるケースでは、体調を整えることが仕事のパフォーマンス維持につながります。
必要に応じて、職場に自分の聞こえにくさを伝えることも検討しましょう。カミングアウトのタイミングや方法は個人差がありますが、周囲の理解が得られれば、支援や配慮も受けやすくなります。
職場における合理的配慮の例
感音性難聴のある人に対して、職場が行える配慮はさまざまです。例えば、職場全体に対して「話すときは相手の顔を見て、ゆっくり・はっきりと伝える」といった基本的なコミュニケーションスタイルを浸透させるだけでも、大きな違いが生まれます。
会議の場では、事前に資料を共有する、発言者を明示する、議事録を残す、必要に応じてマイクや字幕、ホワイトボードを活用するといった工夫が効果的です。電話対応が困難な場合には、別のスタッフに依頼する体制を整える、メール・チャット・対面対応に切り替えるといった柔軟な対応も考えられます。
また静かな場所で集中して作業できるようにデスク位置を調整する、イヤーマフの使用を許可するなど、音環境への配慮も重要です。筆談ボードやコミュニケーション支援アプリなど、テクノロジーを取り入れることで、より円滑なやりとりが可能になります。
さらに、定期的な面談を通じて困りごとを聞き取ったり、状況の変化に応じたサポートを検討したりすることで、当事者が安心して働ける環境作りにつながります。
感音性難聴の方が活用できる支援制度・サービス
感音性難聴の方が生活していく上で、社会制度を活用することも選択肢の一つです。聴力に障がいがある方を対象とした公的支援制度やサービスは多数あり、利用することで経済的・社会的な負担を軽減し、生活や就労の幅を広げられます。
ここでは、感音性難聴のある方が活用しやすい主な制度やサービスを紹介します。
障がい者手帳(聴覚障がい)
一定以上の聴力低下がある場合、身体障がい者手帳(聴覚障がい)の交付を受けることが可能です。手帳を取得することで、税制上の優遇措置(所得税・住民税の控除など)、公共交通機関や携帯電話料金の割引、障がい者向けの福祉サービスの利用など、さまざまな支援を受けられるようになります。
手帳の等級は、聴力レベル(デシベル数)によって決定され、両耳の状態が基準となります。申請はお住まいの市区町村の窓口で受け付けており、耳鼻咽喉科での聴力検査結果や医師の診断書が必要です。
障がい年金
感音性難聴が日常生活や就労に著しい制限をもたらす場合には、障がい年金の対象となることがあります。障がい基礎年金または障がい厚生年金のどちらかが適用されるかは、加入している年金制度により異なります。
受給のためには、初診日が明確であること、一定期間の保険料納付をしていること、障がいの程度が基準を満たしていることが求められます。手続きは年金事務所で行い、医師の診断書や障がいの状況を証明する書類が必要です。
補聴器購入費用の助成・給付
補聴器の購入には高額な費用がかかることがありますが、一定の条件を満たす方は、障害者総合支援法に基づく「補装具費支給制度」を利用できます。これは、身体障がい者手帳の取得者に対して、補聴器などの必要な補装具の購入費用を公的に補助する制度です。
助成を受けるには、自治体の窓口での申請が必要であり、医師の意見書や見積書などが求められます。所得に応じて一部自己負担が生じますが、負担割合は世帯の収入状況によって異なります。
就労支援サービス
感音性難聴がありながら働くことを希望する方は、国や自治体が提供する就労支援サービスを利用できます。例えば、ハローワークには障がい者専用の相談窓口が設置されており、就職活動のサポートや求人情報の提供が可能です。
また独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する「障害者職業センター」では、職業評価、適職の提案、リワーク支援、職場適応訓練などを受けられます。
「就労移行支援事業所」も選択肢の一つです。面接練習や職場実習などを通じて日常生活や就業に必要なスキルを習得し、段階的に職場復帰を目指せます。
まとめ
感音性難聴は、内耳や聴神経など「音を感じ取る部分」の機能に障がいが生じることで発症する難聴です。
一般的に感音性難聴は完治が難しいと言われていますが、適切な医療的対応や補聴器・人工内耳の活用、職場での配慮や社会資源の利用によって、生活の質を保ち、自分らしく働き続けることは十分に可能です。そのためには、何よりも早期の気づきと対処が重要です。
また一人で抱え込まず、耳鼻咽喉科の専門医や福祉・就労支援機関に相談することも大切です。就労移行支援事業所「ココルポート」では、個別支援計画に基づいたスキルトレーニングやリワーク支援、職場体験、定着支援などを提供しています。
支援プログラムは600種類以上と豊富で、パソコンやビジネスマナーなどの実践的なスキルだけではなく、コミュニケーションやセルフマネジメントの力も養えるよう設計されています。
感音性難聴と向き合いながら、より良い生活と働き方を実現するために、本記事が一つの手がかりとなれば幸いです。
監修者情報
こんなお困りありませんか?
以下はよくご相談いただく課題やお悩みの例になります。
ご自身にあてはまる課題やお悩みをクリックするとご提案の例が表示されますのでぜひご参考にしていただければと思います。
チャレンジすることに不安があるかもしれませんが、Cocorportは「失敗できる場」なので、ぜひいろいろなことにチャレンジしていただければと思います。
-
自己分析(理解)
-
対人コミュニケーション
-
体力・生活リズムストレス耐性
-
職場定着・相談先
-
就職活動・スキル
関連記事
関連アイテムはまだありません。
- お電話はこちら
- 0120-336-866
※お電話受付時間 9:00~18:00(日曜定休)

お気軽にお問合せください!
開催予定の就労移行支援の説明会情報
-
秦野駅前Office
★Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料)★ -
大船Office
大船Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料) -
博多Office
Cocorport 博多Officeで就職活動をはじめませんか? -
Cocorport Rework 新横浜駅前
新横浜で、もう一度働きたいあなたへ。メンタル疾患からの復職を専門チームが支えます -
Cocorport Rework 横浜西口
横浜で、もう一度働きたいあなたへ。メンタル疾患からの復職を専門チームが支えます -
横浜戸塚Office
随時受付中✨横浜戸塚Officeに見学に来ませんか?見学会&相談会(参加無料) -
川越Office
Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料)※プログラム体験会も開催中 -
名古屋栄Office
Cocorport 名古屋栄Office見学会&就職個別相談会のお知らせ(参加無料) -
目黒駅前Office
Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料) -
所沢第3Office
Office見学会&就職個別相談会のお知らせ(参加無料)
Officeブログ新着情報
-
春日部駅前Office 2026/02/09
【部署制度紹介】環境部🧹 -
秦野駅前Office 2026/02/09
【利用者さん作成ブログ】ココルポートに通所を決めた理由 -
武蔵浦和Office 2026/02/09
🖊️新しい本を購入しました!📚 -
横浜関内Office 2026/02/09
🔥「模擬面接」で自信を付ける3つのステップ🔥 -
津田沼Office 2026/02/09
★2026年2月のプログラム紹介★ -
所沢第3Office 2026/02/06
プログラム紹介「ビジネス文書のルールとマナー」 -
登戸Office 2026/02/06
【登戸Office】グループワークでオリジナル人生ゲーム作成中🐣 -
新浦安駅前Office 2026/02/06
🧮模擬就労~残業状況集計~のご紹介🧮 -
立川駅前Office 2026/02/06
【トレイニーさんブログ】「HSP」について -
北千住Office 2026/02/06
【2月前半開催プログラム紹介】メリハリある時間管理術🕙