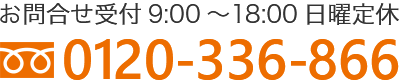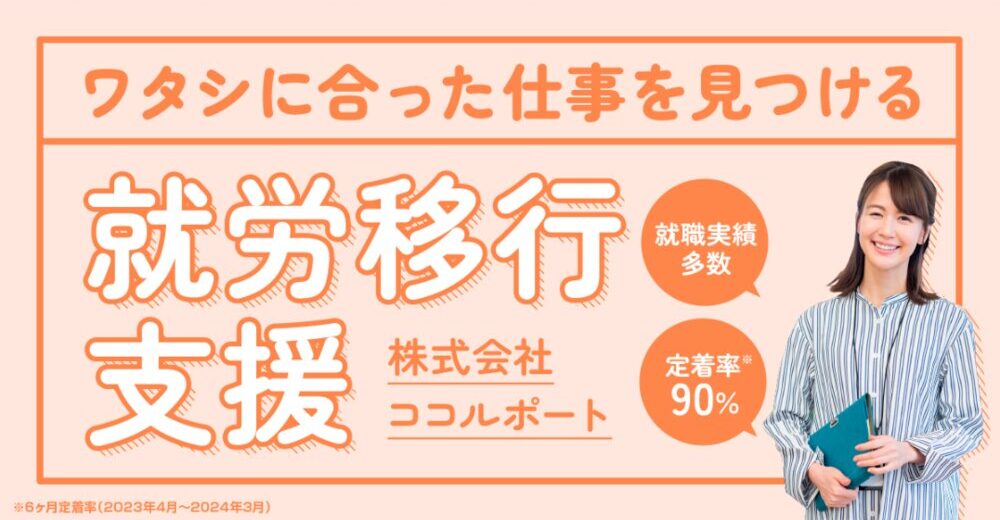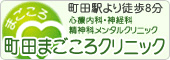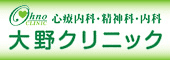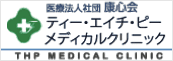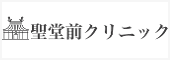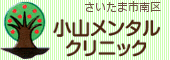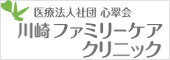- ココルポート(就労移行支援・定着支援/自立訓練/計画相談) HOME
- お役立ち情報
- 診断書を会社に提出するタイミングはいつ? 記載内容・手続き・注意点を解説
診断書を会社に提出するタイミングはいつ? 記載内容・手続き・注意点を解説
公開日:2025/08/18
更新日:2025/08/18

体調不良やけがなどで会社を長期間休む必要が生じたとき、会社から「診断書の提出」を求められるケースは少なくありません。 しかし、いざ診断書が必要となると、「いつまでに提出すればいいのか」「どのような内容が書かれていれば良いのか」「手続きはどう進めるべきか」など、戸惑いや不安を感じる方もいるのではないでしょうか。
本記事では、会社へ提出する診断書の基本的な役割から、提出すべきタイミング、記載内容のポイント、提出後の流れ、注意すべき点までを網羅的に解説します。
診断書を通じて会社と円滑にやり取りし、適切なサポートを受けながら療養や復職に臨むために、知っておくべき実務的なポイントを分かりやすく丁寧にお伝えします。
目次
会社へ提出する診断書の基本的な役割

診断書は、医師が患者の病状やけがの状態、治療に必要な期間、業務上の配慮事項などを医学的な根拠に基づいて証明する書類です。
単なる自己申告ではなく、専門家である医師の判断を示す公的な証明として扱われるため、欠勤や休職、職場での業務調整の可否を判断する上で重要な役割を果たします。
会社が診断書の提出を求める理由
会社が従業員に診断書の提出を求める背景には、いくつかの目的があります。第一に、労働者の健康状態を客観的かつ正確に把握することです。体調不良が疑われる場合でも、会社が独自に判断することはできないため、専門医による診断書が必要です。
また会社には労働契約法第5条に定められた「安全配慮義務」が課されています。これは、従業員が安心して働ける環境を整備し、生命や身体の安全を守るための義務であり、診断書はその履行に必要な情報を提供します。
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
さらに、休職の可否や復職のタイミング、就業制限の必要性などを判断する上でも、診断書が必要です。
加えて、傷病手当金などの社会保険給付を申請する場合、会社が申請に協力するためには、診断書によって従業員の状況を確認する必要があります。
診断書提出の義務について
診断書の提出義務が生じるかどうかは、主に労働契約や就業規則の内容によって判断されます。多くの企業では「一定日数以上の欠勤があった場合は診断書を提出すること」といった規定を設けています。そのため、まずは就業規則の内容を確認することが重要です。
企業側が合理的な根拠に基づいて診断書の提出を求めているにもかかわらず、従業員が正当な理由なく拒否した場合、懲戒処分や無断欠勤扱い、休職・復職の不許可など、労働条件に関する不利益を被る可能性があります。
ただし、業務に直接関係のない私傷病の詳細や、過度にプライバシーに踏み込んだ情報まで提出を強要することは、法的に問題となる可能性があります。
診断書を会社に提出すべき具体的なタイミング

診断書の提出タイミングは、就業規則や会社からの指示内容に左右されるため、まずは社内ルールを確認することが前提です。
原則として、医師から休職や復職についての指示を受けた場合や、会社から診断書の提出を求められた場合には、速やかに提出する必要があります。
診断書を会社に提出すべき具体的なタイミングについて詳しく見ていきましょう。
病気やけがで会社を休むとき
医師から休職が必要と診断された場合は、診断を受けた直後に、まず上司や人事担当者へ口頭で報告し、診断書を提出予定である旨を伝えるのが適切です。
診断書は医師に依頼して作成してもらい、入手後は会社の定める期限(例:数日〜1週間以内)に従って速やかに提出しましょう。
就業規則に「◯日以上の欠勤がある場合は診断書の提出を要する」といった規定が設けられていることもあります。
休職期間を延長するとき
当初の休職期間内で十分な回復が見込めず、延長が必要となる場合は、主治医と相談した上で新たに診断書を取得しましょう。
休職期間が満了する前に、会社へ延長の意思を伝えるとともに、再発行された診断書を提出する必要があります。
延長手続きには期限や所定の書式が設けられている場合があるため、あらかじめ人事担当者に必要事項を確認しておきましょう。
会社へ復職を申し出るとき
復職を希望する際には、まず主治医にその意思を伝え、就労可能と判断された上で復職診断書の作成を依頼します。
診断書には、「復職可能」「就業上の配慮事項あり/なし」などの具体的な記載が必要です。
作成された復職診断書を添えて会社へ復職の意向を伝えた後、会社側では産業医による面談や社内基準に基づき、最終的な復職の可否が判断されます。
会社提出用の診断書の記載内容
会社へ提出する診断書には、就業可否の判断や業務上の配慮のために必要な情報が網羅的に記載されます。以下のような内容が含まれます。
- ・患者に関する基本情報:氏名・生年月日・性別・住所など
- ・医療機関に関する情報:病院名、所在地、診療科名、担当医師の氏名・連絡先、医師の押印
- ・診断に関する情報:傷病名(例:うつ病、適応障がい、腰椎椎間板ヘルニアなど)、発病・受傷年月日、症状の経過や主な症状、必要に応じて検査結果
- ・治療に関する情報:現在行っている治療内容、治療経過、今後の治療期間の見込み
- ・就業に関する医師の意見:療養期間(例:「〇年〇月〇日から約〇カ月間の自宅療養が必要」)、就業の可否(例:「現時点では就労困難」「〇年〇月〇日より復職可能」など)
- ・就業上の配慮事項:時間外労働の制限、重量物の取り扱い制限、通院のための勤務時間調整など
- ・その他の記載項目:診断書の作成日、有効期限(設定されている場合)
提出前には、記載内容に誤りや不備がないかを確認しておくことをおすすめします。
医師に診断書作成を依頼する際のポイント
診断書を作成してもらう際は、医師が適切な内容を記載できるよう、必要な情報を正確かつ具体的に伝えることが大切です。会社提出用の診断書の場合、職場とのやり取りや就業状況を医師が把握していないケースも多いため、以下の点を意識して依頼しましょう。
まずは、会社から診断書の提出を求められた経緯や目的を明確に伝えることが基本です。「休職の申請に必要」「復職の判断材料として提出する」「就業上の配慮をお願いしたい」など、具体的な用途を共有することで、診断書の内容もより適切なものになります。
会社から指定の様式やフォーマットがある場合は、必ず持参して提示しましょう。また会社が特に記載を求めている項目(例:「復職可能日の明記」「配慮事項の有無」など)がある場合は、事前にメモしておき、診察時に伝えるとスムーズです。
併せて、自身の仕事内容や職場環境、どのような業務で困難を感じているかについても、できるだけ具体的に説明することが重要です。
「長時間のパソコン作業が集中力を削ぐ」「対人応対で強いストレスがある」など、業務との相性や不調の背景を補足すると、医師による診断内容や就業上の配慮に反映されやすくなります。
また希望する休職期間や勤務上の配慮があれば、それも遠慮なく相談しましょう。最終的な判断は医師が行いますが、状況を共有することで、診断書の内容が実情に即したものになりやすくなります。
診断書の提出手続き
診断書を医師から受け取ったら、速やかに会社へ提出しましょう。しかし、提出方法を誤るとトラブルや再提出を求められることもあるため、手続きの流れや注意点をしっかり押さえておくことが大切です。ここでは、診断書提出時の具体的なステップとマナーについて解説します。
診断書の内容を確認する
提出前には、診断書に記載された内容を必ず確認しましょう。氏名・生年月日・発行日などの情報、医師の署名や押印があるか、就業制限や療養期間など、会社から求められている情報が漏れなく記載されているかをチェックします。
規則で定められた担当者に提出する
診断書の提出先は、会社ごとに就業規則や社内マニュアルで定められていることが多く、「直属の上司」「人事部」「総務部」などが一般的です。不明な場合は、上司や人事担当者に確認しましょう。
提出は原本を手渡しするのが基本ですが、出社が難しい場合や遠隔勤務中は、郵送やメールでの提出が認められることもあります。その際は事前に提出方法を確認し、郵送の場合は配達記録が残る方法(簡易書留、特定記録郵便など)を利用すると良いです。
メール送信時はPDF形式で添付し、保存用にも控えを残しておきましょう。
診断書提出時のビジネスマナーと伝え方
診断書を提出する際には、一言添えると印象がよくなります。例えば「ご迷惑をおかけしますが、しばらく療養に専念させていただきます」「ご対応ありがとうございます」といった一文を添えて提出しましょう。
また今後の連絡方法や休職中の必要な手続きについても、併せて確認しておくと安心です。メールで提出する場合は、件名に「診断書提出(氏名)」と明記し、本文でも簡潔かつ丁寧な言葉遣いで送信します。
文面例としては、「○月○日付で医師より診断書を受け取りましたので、添付の通りご提出申し上げます。今後のご対応についてご確認いただけますと幸いです」といった表現が一般的です。
診断書を提出した後の流れ
診断書を会社に提出した後は、就業規則や社内制度に沿って、休職や復職に関する手続きが進められます。
通常は、会社から休職期間の決定、休職中の連絡方法、社会保険関連の手続き(傷病手当金の申請など)、復職時の段取りについて説明があります。こうした案内を受けた際は、不明な点をそのままにせず、必ず確認して指示に従いましょう。
休職の開始や復職の判断に際して、産業医による面談が設定されることも一般的です。医師の診断書と産業医の意見を基に会社側が最終的な判断を行うため、面談には真摯な姿勢で臨むことが求められます。
休職中は療養に専念することが優先ですが、長期にわたる場合や不安を感じる場合には、会社と適切なコミュニケーションを保つことも重要です。連絡が途絶えると、復職時に手続きがスムーズに進まないケースもあるため、状況に応じた報告や相談を心掛けましょう。
「復職後の働き方が不安」「再発を防ぐためにどう過ごせばいいか分からない」といった悩みがある場合は、医療機関が提供するリワーク支援や就労移行支援事業所、自治体の相談窓口などを活用するのも方法の一つです。
診断書に関するよくある質問
会社への診断書提出に当たっては、「どこまでの情報を記載すべきか」「診断名の伝え方はどうするか」「費用や日数はどれくらいかかるのか」といった疑問を抱える方も多くいます。
ここでは、診断書に関してよく寄せられる質問について、具体的に解説します。
会社が診断書で確認しているポイントは?
会社が診断書を通じて重視しているのは、従業員が現在就労できる状態か、あるいは一定期間の休養が必要かという医学的な根拠です。
これは、企業が安全配慮義務(労働契約法第5条)を果たすために不可欠な情報であり、無理な就労によって健康状態が悪化することを防ぐ目的があります。
また実務面でも、休職の可否に応じて人員配置や業務の調整、代替要員の確保が必要となるため、会社としてもできるだけ正確な情報を把握したいと考えています。
診断書に記載された療養期間は、傷病手当金の申請にも活用され、申請時の基準となることもあります。
さらに、スムーズな職場復帰や再発防止の観点から、「短時間勤務の配慮」や「業務負担の調整」など、合理的配慮の具体的な内容も重要です。診断書にこうした配慮事項が明記されていると、会社としても復職支援の方針を立てやすくなります。
診断書の記載内容に関する相談はできる?
診断書に記載される内容については、医師と相談しながら調整することが可能です。特に精神疾患など、診断名の開示に抵抗がある場合は、「どこまで会社に伝えるか」を事前に話し合うことをおすすめします。例えば「うつ病」や「適応障がい」といった具体的な病名の記載を避け、「心身の不調による休養が必要」といった表現にとどめてもらうこともできます。
また職場での就業判断に直接関係しないような、私的な背景や詳細な症状については、プライバシー保護の観点から、記載を控えてもらうようお願いすることも可能です。
診断書はあくまで、労働に影響があるかどうかを判断するための書類です。不明な点や不安な点がある場合は、遠慮せず医師に質問し、自分が納得した上で作成を依頼しましょう。
診断書の作成費用や発行にかかる時間は?
診断書の作成費用は健康保険の適用外のため、全額自己負担です。金額は医療機関によって異なりますが、一般的には数千円程度が相場です。種類や内容、診断書の様式によっては、より高額になるケースもあるため、事前に確認しておきましょう。
また診断書が即日で発行されるとは限らず、数日〜1週間ほどかかる場合もあります。特に繁忙期や医師の診察スケジュールによっては、さらに日数がかかることもあるため、会社への提出期限がある場合には、できるだけ早めに依頼しておきましょう。発行までの所要日数については、受付や医師に確認することをおすすめします。
まとめ
診断書を会社に提出する際は、タイミング・記載内容・手続きの流れ・医師への依頼方法など、いくつかの重要なポイントを押さえておくことが大切です。
記載内容に不安がある場合や提出に迷いがあるときは自己判断せず、医師や会社の人事・労務担当者に相談しましょう。労働基準監督署や弁護士、社会保険労務士などに助言を求めることも可能です。
また休職中や復職前後の不安が大きい方は、リワーク支援などを行う外部の専門機関の利用も選択肢の一つです。例えば「ココルポート」では、うつ病・発達障がい・双極性障がいなどがある方に対して、復職支援・就労移行支援を提供しており、安心して次のステップに進むためのサポートを受けることができます。
本記事が、診断書の提出に関して不安や疑問を抱える方にとって道しるべとなり、自信を持って対応できるようになれば幸いです。
こんなお困りありませんか?
以下はよくご相談いただく課題やお悩みの例になります。
ご自身にあてはまる課題やお悩みをクリックするとご提案の例が表示されますのでぜひご参考にしていただければと思います。
チャレンジすることに不安があるかもしれませんが、Cocorportは「失敗できる場」なので、ぜひいろいろなことにチャレンジしていただければと思います。
-
自己分析(理解)
-
対人コミュニケーション
-
体力・生活リズムストレス耐性
-
職場定着・相談先
-
就職活動・スキル
関連記事
関連アイテムはまだありません。
- お電話はこちら
- 0120-336-866
※お電話受付時間 9:00~18:00(日曜定休)

お気軽にお問合せください!
開催予定の就労移行支援の説明会情報
-
秦野駅前Office
★Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料)★ -
大船Office
大船Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料) -
博多Office
Cocorport 博多Officeで就職活動をはじめませんか? -
Cocorport Rework 新横浜駅前
新横浜で、もう一度働きたいあなたへ。メンタル疾患からの復職を専門チームが支えます -
Cocorport Rework 横浜西口
横浜で、もう一度働きたいあなたへ。メンタル疾患からの復職を専門チームが支えます -
横浜戸塚Office
随時受付中✨横浜戸塚Officeに見学に来ませんか?見学会&相談会(参加無料) -
川越Office
Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料)※プログラム体験会も開催中 -
名古屋栄Office
Cocorport 名古屋栄Office見学会&就職個別相談会のお知らせ(参加無料) -
目黒駅前Office
Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料) -
所沢第3Office
Office見学会&就職個別相談会のお知らせ(参加無料)
Officeブログ新着情報
-
春日部駅前Office 2026/02/09
【部署制度紹介】環境部🧹 -
秦野駅前Office 2026/02/09
【利用者さん作成ブログ】ココルポートに通所を決めた理由 -
武蔵浦和Office 2026/02/09
🖊️新しい本を購入しました!📚 -
横浜関内Office 2026/02/09
🔥「模擬面接」で自信を付ける3つのステップ🔥 -
津田沼Office 2026/02/09
★2026年2月のプログラム紹介★ -
所沢第3Office 2026/02/06
プログラム紹介「ビジネス文書のルールとマナー」 -
登戸Office 2026/02/06
【登戸Office】グループワークでオリジナル人生ゲーム作成中🐣 -
新浦安駅前Office 2026/02/06
🧮模擬就労~残業状況集計~のご紹介🧮 -
立川駅前Office 2026/02/06
【トレイニーさんブログ】「HSP」について -
北千住Office 2026/02/06
【2月前半開催プログラム紹介】メリハリある時間管理術🕙