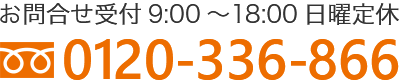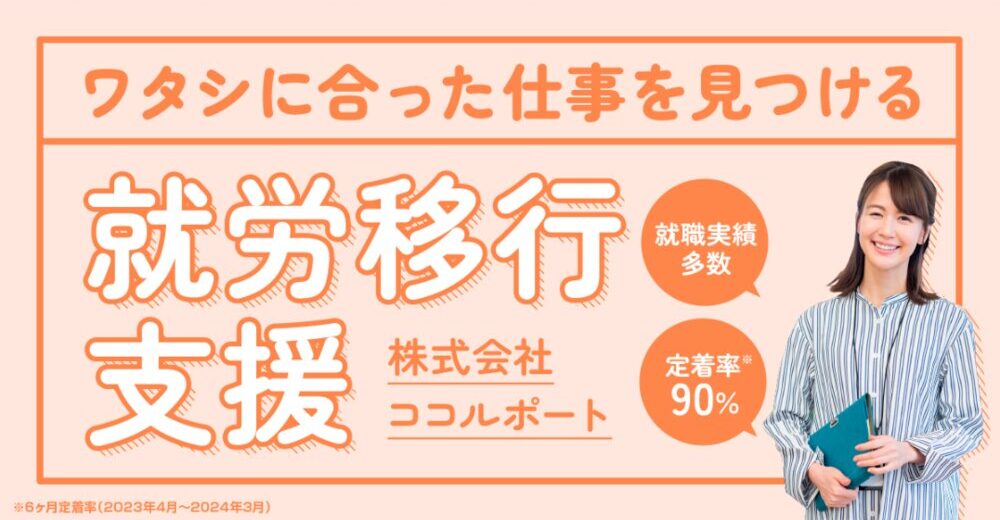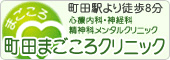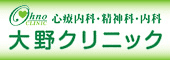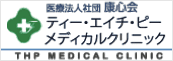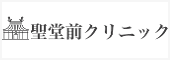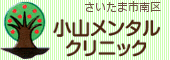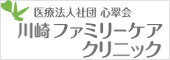- ココルポート(就労移行支援・定着支援/自立訓練/計画相談) HOME
- お役立ち情報
- 【初心者向け】自律訓練法のやり方|効果と注意点も解説
【初心者向け】自律訓練法のやり方|効果と注意点も解説
公開日:2025/10/02
更新日:2025/10/02

現代社会において、慢性的なストレスや心身の不調を抱える方は少なくありません。こうした状況の中、自身で心身のバランスを整える手法として注目されているのが「自律訓練法」です。
「専門的で難しそう」「本当に効果があるのだろうか」と感じる方も多いかもしれませんが、自律訓練法は、基本的な知識と正しい方法を身に付ければ、誰でも自宅で取り組めるセルフケア法です。
本記事では、自律訓練法の理論や背景、基本的な実践方法などを、初心者にもわかりやすく体系的に解説します。日常生活に無理なく取り入れられるリラクゼーション法の一つとして、ぜひ参考にしてください。
目次
自律訓練法とは? 心と体をリラックスさせるセルフケア

自律訓練法とは、心身の緊張を和らげ、自律神経のバランスを整えるためのセルフケア法です。決まった姿勢や言葉を用いて自己暗示を行い、意図的にリラックス状態を作り出します。専門家の指導の下で治療法として活用されることもありますが、正しいやり方を身に付ければ、自宅や職場でも手軽に実践できるのが特徴です。ここでは、自律訓練法の成り立ちや仕組み、どのような人に適しているのかを解説します。
自律訓練法の成り立ちと目的
自律訓練法は、1932年にドイツの精神科医J・H・シュルツ博士によって体系化された自己催眠法・リラクゼーション法です。シュルツ博士は、催眠状態に入った人が手足の温かさや重さを感じる現象に着目し、誰でも自己暗示によって類似のリラックス状態を作り出せる方法として開発しました。
自律訓練法の目的は、心身の緊張を自ら緩め、自律神経(交感神経と副交感神経)のバランスを整えることにあります。医療現場では心療内科や精神科で不安障がいや自律神経失調症などの治療補助として導入される他、スポーツ選手のメンタルトレーニングや、企業研修などでも幅広く活用されています。
自律訓練法でなぜリラックスできる?
私たちの体は、ストレスを感じると交感神経が優位になり、心拍数の上昇、筋肉の緊張、呼吸の浅さなどが生じます。これに対し、副交感神経が優位になると心身はリラックスし、血流や消化機能も改善されます。
自律訓練法は、決まった言葉(言語公式)を繰り返し唱えながら体の各部位に意識を向け、自己暗示を通じて副交感神経を活性化します。こうして睡眠と覚醒の中間のような「自己催眠状態」を作り出すことで、ストレスを緩和しながら深いリラクゼーション効果を得られるのです。
自律訓練法はこのような人におすすめ
自律訓練法は、次のような悩みや目的を持つ方に適しています。
- ・日常的にストレスや不安を感じやすい方
- ・緊張しやすく、プレゼンや試験前にあがりやすい方
- ・寝つきが悪い、眠りが浅いなど不眠傾向にある方
- ・肩こりや頭痛、冷え性などの身体的不調を感じる方
- ・集中力を高めたいと考えている方
- ・自分の感情や行動をセルフコントロールしたい方
特別な道具も不要で、自分のペースで継続しやすいため、取り入れやすいセルフケア方法の一つといえます。
自律訓練法で期待できる効果
自律訓練法は、心と体の両面に働きかけるセルフケア法です。継続的に実践することで、ストレス軽減から体調管理、さらには仕事や学習でのパフォーマンス向上まで、幅広い効果が期待できます。ここでは、自律訓練法によって得られる具体的なメリットを、心・体・パフォーマンスの3つの側面に分けて紹介します。
心への効果:ストレス軽減と精神的な安定
自律訓練法を行うことで、副交感神経が優位になり、気分の安定やストレス耐性の向上が期待できます。特に次のような効果が報告されています。
- ・日常的な不安感やイライラ感を軽減できる
- ・気分の落ち込みや不安定な感情を改善できる
- ・精神的な落ち着きが得られ、気持ちに余裕が生まれる
- ・自分で心身をコントロールできる感覚が高まり、自己肯定感の向上につながる
ストレスを感じやすい現代社会において、精神面の安定は生活の質の向上にも直結します。
体への効果:緊張緩和と不調の改善
自律訓練法は筋肉の緊張を和らげ、血流や内臓機能にも良い影響を与えるとされています。具体的には以下のような身体的効果が期待できます。
- ・肩こりや頭痛など筋肉の緊張による不調を軽減できる
- ・血行促進による冷え性や末端の冷えを改善できる
- ・入眠しやすくなる、眠りが深くなる
- ・日々の疲労感が軽減し、疲労回復が早まる
- ・胃腸の不調や便秘・下痢などが改善する
- ・ストレスが関係する動悸や息苦しさなどの身体症状が緩和する
体が整うことで、心の安定にも良い影響が生まれます。
パフォーマンスへの効果:集中力・自己統制力の向上
自律訓練法を続けることで、日常生活や仕事・勉強などの場面でもメリットが得られます。
- ・緊張や動揺を抑えられ、集中力が高まる
- ・感情のコントロールがしやすくなり、人間関係や仕事の場面でも落ち着きを維持しやすくなる
- ・試験やプレゼン、スポーツの大会など、プレッシャーのかかる場面でも実力を発揮しやすくなる
なお、自律訓練法の効果には個人差があります。特に病気の治療や症状の改善を目的とする場合は、必ず医師や専門家に相談し、指導を受けた上で実施してください。
自律訓練法の基本的なやり方
自律訓練法は、決められた言葉(公式)を心の中で唱えながら、心身をリラックス状態へと導くセルフケアです。ここでは、初心者の方でも実践しやすい「標準練習」の基本手順を、わかりやすく解説します。
なお、背景公式含む全部で7つある公式のうち、第3公式〜第6公式は練習法が難しく、持病や体質、体調によって合わないリスクがあります。一人で行わずに自律訓練法認定士や医師など専門家の指導のもと行うことをおすすめします。
ここでは背景公式と第1公式、第2公式の3つと消去動作をご紹介します。
リラックスできる環境と姿勢を整える
まずは、実践に適した環境と姿勢を整えましょう。
実践する際は、静かで、電話や話しかけなどの邪魔が入らない落ち着いた空間を選ぶのがおすすめです。また体を締め付けない、ゆったりとした服装に着替えましょう。
実践する前にトイレを済ませ、アクセサリーや時計、眼鏡などは外します。部屋を少し暗めにすると、よりリラックスしやすくなるでしょう。
次に、姿勢を以下のどちらかに決めます。
基本姿勢①(仰向け:仰臥位)
布団やマットの上に仰向けに寝ます。両足は肩幅程度に軽く開き、両腕もわずかに体から離して手のひらは上向きまたは下向きにして全身の力を抜きましょう。
基本姿勢②(椅子に座る:単純椅子姿勢)
背もたれのない椅子に深く腰掛け、背筋は軽く伸ばします。両足は肩幅程度に開き、足裏は床にしっかり付けます。口元は軽く開け、上下の歯が触れない程度にリラックスさせましょう。
どちらの場合も、目を軽く閉じ、体全体の緊張を緩める意識を持ちます。
「受容的注意」と「公式への集中」の心構え
自律訓練法では、「リラックスしよう」「感じなければ」と努力するのではなく、自然に湧き上がる感覚をそのまま受け止める受容的態度が大切です。これから紹介する公式の言葉を心の中でゆっくり繰り返しながら、感覚が生じるのを静かに待つイメージで取り組みましょう。
背景公式:リラックスの土台作り
最初は背景公式から始めます。深呼吸を数回繰り返し、息を吐くたびに肩や全身の力を抜いていきます。
気持ちが落ち着いてきたら、心の中で「気持ちが(とても)落ち着いている」と繰り返します。無理に落ち着かせようとせず、「自然と今、落ち着いている」と感じるのがこつです。
第1公式:重感練習(手足の重さを感じる)
次に重感練習を行います。手足の重さを順に意識します。
1.右腕が重たい
2.左腕が重たい
3.両腕が重たい
4.右脚が重たい
5.左脚が重たい
6.両脚が重たい
感覚が得られなくても焦らず、ゆっくり言葉を反復しましょう。語尾を伸ばすように「重たーい」と唱えるのも効果的です。
第2公式:温感練習(手足の温かさを感じる)
続いて温感練習です。血流が増え温かくなる感覚を味わいます。
1.右腕が温かい
2.左腕が温かい
3.両腕が温かい
4.右脚が温かい
5.左脚が温かい
6.両脚が温かい
この温かさはリラックスに伴う自然な生理反応です。無理に温めようとせず、現れる感覚をそのまま受け入れます。
消去動作
自立訓練法を終える際には、消去動作を行い、心身を自己暗示状態から目覚めさせます。
- ・手足を強く握ったり、開いたりする
- ・両手を組んで大きく伸びをする
- ・首や肩を回す
※入眠前であれば、消去動作を行わず、そのまま眠りに入れば問題ありません
自律訓練法の効果を高める! 練習のポイントとコツ

自律訓練法は、繰り返しの練習によって少しずつ心身がリラックスしやすくなっていく訓練です。ここでは、練習をより効果的に進めるための具体的なポイントや継続のコツを紹介します。
練習時間と頻度の目安
初心者は1回3〜5分程度から始めるのがおすすめです。慣れてきたら徐々に 5〜10分程度まで延ばしていきます。
適切な頻度は、1日2〜3回です。例えば、朝起きた直後や昼休みなどの休憩時間、夜寝る前など、日常生活の中に自然に組み込むと続けやすいです。
無理のない範囲で毎日続けることで、効果を得やすくなるでしょう。
「受容的態度」を常に意識
効果を急ごうとしたり、完璧を目指したりする必要はありません。感覚が得られなくても「今はそれで良い」 と受け入れる姿勢が重要です。
練習中に雑念や考え事が浮かんできても、無理に追い払おうとせず、自然に受け流しましょう。この受容的態度を持つこと自体が、自律訓練法の練習の一部です。
感覚が得にくいときのヒント
感覚が得にくい場合は、公式の言葉をゆっくり優しい口調で心の中で唱えてみましょう。また、利き手・利き足から始めると、感覚を得やすい場合があります。
お風呂上がりなど体が温まっているときは、よりリラックスしやすくなります。
感覚を無理に作り出そうとせず、あくまで自然に感じるのを待ちましょう。
練習記録を取る
練習した日時・場所・練習した公式・感じた感覚などを簡単にメモしておくと、自分の進歩が見えやすくなります。体の反応や効果の違いが分かりやすくなり、モチベーションの維持にもつながります。
小さな変化にも気付きやすくなり、練習の継続がより楽しくなっていくでしょう。
安全に行うために知っておきたい注意点と禁忌
自律訓練法は比較的安全で手軽に行えるセルフケア法ですが、全ての人に適しているわけではありません。安全に行うためには、以下のような注意点と禁忌を理解しておく必要があります。
- ・心臓に異常のある人(不整脈、心不全など)
- ・糖尿病のある人(低血糖などを伴いやすい場合)
- ・頭痛の持病がある人(片頭痛など)
- ・脳波に異常がある人(てんかんなど)
- ・妄想などの精神症状が現れている人
これらに該当する場合、自律訓練法によるリラクゼーションの過程で症状が悪化したり、副作用が生じたりする可能性があります。
すでに医療機関にかかっている方は、必ず主治医に相談した上で実践しましょう。特に第3公式以降の心臓や呼吸、内臓に関わる練習は、専門家の指導を受けながら行ってください。
また自律訓練法を行ったら、消去動作(消去運動)を必ず実施しましょう。消去動作を省略すると、リラクゼーション状態から日常生活に戻る際に、ぼんやり感やめまい、倦怠感などが残るリスクがあります。
不安がある場合は、自己流で無理に進めず、日本自律訓練学会の認定指導士や医療機関の専門家への相談も検討しましょう。
セルフケアに加えて専門的なサポートも視野に
自律訓練法は心身のバランスを整え、日常のストレスケアに役立つ優れたセルフケア法ですが、全ての不調を自力で解決できるわけではありません。
- ・不安やストレスがなかなか軽減しない
- ・睡眠障がいや体調不良が長引いている
- ・仕事や生活に支障が出るほど悩みが深刻になっている
こうした場合は、一人で抱え込まずに専門家のサポートを受けることが大切です。
自律訓練法は、必要に応じて専門的なサポートと併用することで、その効果を最大限に生かせる手法です。
まとめ
自律訓練法は、初心者でも無理なく始められるセルフケアの一つです。日々少しずつ練習を重ねることで、ストレス軽減や心身の不調の改善、集中力の向上など、さまざまな効果が期待できます。
特別な道具や場所を必要としないため、空き時間に取り入れやすいでしょう。
ただし、自律訓練法はあくまでセルフケアの一つであり、全ての悩みや不調を解決できるわけではありません。もし、仕事や生活に関する悩みが深刻化している場合には、一人で抱え込まず、専門的サポート機関に早めに相談することも大切です。
ココルポートでは、障がいのある方に向けた就労移行支援サービスを提供しています。就労に向けたスキルアップはもちろん、セルフケアに関する訓練メニューも多数用意していますので、ぜひご相談ください。自律訓練法と専門家のサポートを上手に活用し、心身の健康維持と充実した毎日を目指していきましょう。
監修者プロフィール
こんなお困りありませんか?
以下はよくご相談いただく課題やお悩みの例になります。
ご自身にあてはまる課題やお悩みをクリックするとご提案の例が表示されますのでぜひご参考にしていただければと思います。
チャレンジすることに不安があるかもしれませんが、Cocorportは「失敗できる場」なので、ぜひいろいろなことにチャレンジしていただければと思います。
-
自己分析(理解)
-
対人コミュニケーション
-
体力・生活リズムストレス耐性
-
職場定着・相談先
-
就職活動・スキル
関連記事
関連アイテムはまだありません。
- お電話はこちら
- 0120-336-866
※お電話受付時間 9:00~18:00(日曜定休)

お気軽にお問合せください!
開催予定の就労移行支援の説明会情報
-
秦野駅前Office
★Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料)★ -
大船Office
大船Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料) -
博多Office
Cocorport 博多Officeで就職活動をはじめませんか? -
Cocorport Rework 新横浜駅前
新横浜で、もう一度働きたいあなたへ。メンタル疾患からの復職を専門チームが支えます -
Cocorport Rework 横浜西口
横浜で、もう一度働きたいあなたへ。メンタル疾患からの復職を専門チームが支えます -
横浜戸塚Office
随時受付中✨横浜戸塚Officeに見学に来ませんか?見学会&相談会(参加無料) -
川越Office
Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料)※プログラム体験会も開催中 -
名古屋栄Office
Cocorport 名古屋栄Office見学会&就職個別相談会のお知らせ(参加無料) -
目黒駅前Office
Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料) -
所沢第3Office
Office見学会&就職個別相談会のお知らせ(参加無料)
Officeブログ新着情報
-
春日部駅前Office 2026/02/09
【部署制度紹介】環境部🧹 -
秦野駅前Office 2026/02/09
【利用者さん作成ブログ】ココルポートに通所を決めた理由 -
武蔵浦和Office 2026/02/09
🖊️新しい本を購入しました!📚 -
横浜関内Office 2026/02/09
🔥「模擬面接」で自信を付ける3つのステップ🔥 -
津田沼Office 2026/02/09
★2026年2月のプログラム紹介★ -
所沢第3Office 2026/02/06
プログラム紹介「ビジネス文書のルールとマナー」 -
登戸Office 2026/02/06
【登戸Office】グループワークでオリジナル人生ゲーム作成中🐣 -
新浦安駅前Office 2026/02/06
🧮模擬就労~残業状況集計~のご紹介🧮 -
立川駅前Office 2026/02/06
【トレイニーさんブログ】「HSP」について -
北千住Office 2026/02/06
【2月前半開催プログラム紹介】メリハリある時間管理術🕙