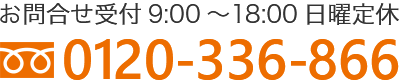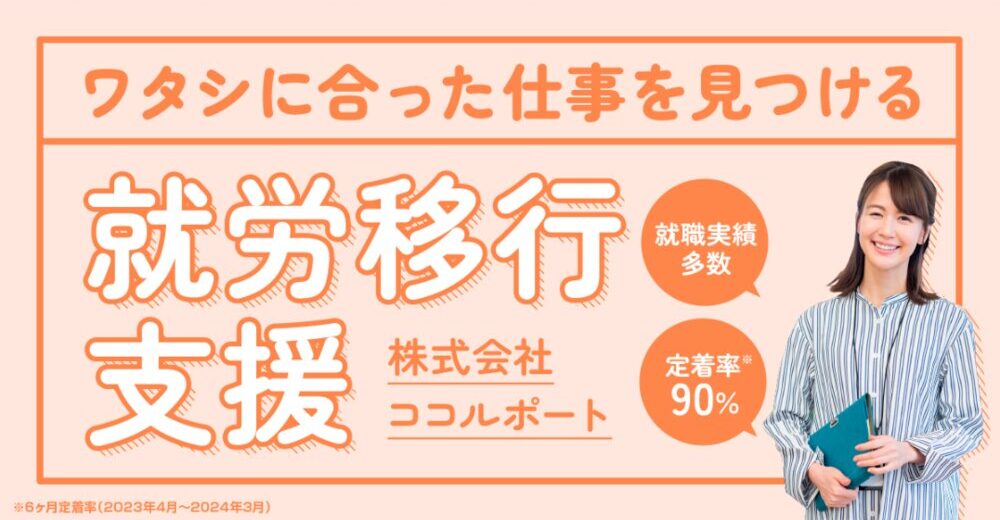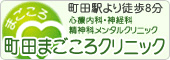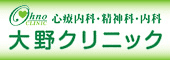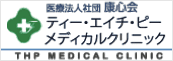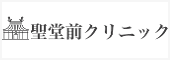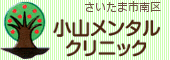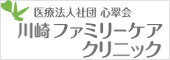- ココルポート(就労移行支援・定着支援/自立訓練/計画相談) HOME
- お役立ち情報
- 就労移行支援はお金がない場合でも利用できる?支援制度や相談先について解説
就労移行支援はお金がない場合でも利用できる?支援制度や相談先について解説
公開日:2025/10/02
更新日:2025/10/02

「就労移行支援を受けてみたいけれど、費用が心配で一歩が踏み出せない」このような不安を抱える方は少なくありません。
しかし、就労移行支援は多くの方が自己負担なしで利用できる障がい福祉サービスです。世帯の収入状況によっては月額負担が発生するケースもありますが、それ以外にもさまざまな支援制度や補助を受けることができます。
本記事では「お金がないけど就労移行支援を利用したい」という方に向けて、費用の仕組みや活用できる支援制度、経済的な不安を軽くする方法を分かりやすく解説します。
目次
就労移行支援とは?

就労移行支援は、障がいや難病のある方が一般企業への就職を目指すために利用できる、障がい福祉サービスのひとつです。単に就職活動を支援するだけではなく、日々の生活リズムの安定やスキル習得、面接対策など、就職に必要な準備を総合的にサポートします。
さらに、就職後も長く働き続けられるよう、職場への定着支援まで一貫して行われる点が特徴です。
利用できるのは、原則として18歳以上65歳未満で、身体障がいや知的障がい、精神障がい、発達障がい、難病などのある方のうち、一般就労を希望し、就労の可能性があると判断された方です。現在離職中であっても利用することができ、将来の就職に向けて一歩を踏み出したい方にとって、大きな支えとなるでしょう。
具体的なサービス内容
就労移行支援では、就職に向けた準備から就職後のフォローまで、段階に応じた多様なサポートが受けられます。
例えば、生活リズムの改善や勤怠の安定を図るプログラムで、通所を通じて働くための基礎を整えることができます。
またビジネスマナーやパソコン操作、コミュニケーション力など、就労に必要な知識・スキルの習得も支援内容に含まれるのが特徴です。
履歴書作成のサポートや面接練習など、求職活動に直接関わる支援も充実しています。希望や適性に応じた職場実習の機会も提供され、実際の仕事を体験することで、自分に合った働き方を見つけることが可能です。
就職後には、職場との連絡調整や悩みの相談といった定着支援も継続的に行われます。単なる就職支援にとどまらず「就職してからも働き続けられること」を見据えた包括的なサポートが特徴です。
就労移行支援の利用料

就労移行支援の利用料(自己負担額)は厚生労働省が定めた基準に基づいて決まります。ただし、世帯の収入状況によって自己負担額は異なり、多くの方が自己負担なく利用しているのが実情です。
収入状況ごとの具体的な負担額について詳しく見ていきましょう。
生活保護受給世帯
生活保護を受給している世帯は、就労移行支援の利用料は一切かかりません(自己負担額0円)。
所得判定における「世帯」の範囲は、以下のとおりです。
- 18歳以上の障がい者(施設に入所している18・19歳を除く):障がいのある本人とその配偶者
- 障がい児(施設入所中の18・19歳を含む):保護者が属する住民基本台帳での世帯
※参考:厚生労働省.「障害者の利用者負担」.
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/hutan1.html ,(参照2025-08-05).
市町村民税非課税世帯
市町村民税が非課税となっている世帯も、生活保護世帯と同様に就労移行支援の利用料は無料です。
障がい基礎年金1級を受給している3人世帯の場合、収入がおおよそ300万円以下であれば非課税世帯に該当します。
この区分に該当する世帯も多く、収入に不安があっても利用しやすい制度です。
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)
世帯の収入により市町村民税が課税されている場合でも、所得割が16万円未満(おおむね世帯年収600万円以下)であれば、月額9,300円を上限に利用料が設定されます。
その他の世帯
世帯の所得割が16万円以上、すなわち年収がおおよそ600万円を超える世帯については、就労移行支援の利用料は月額37,200円が上限となります。
負担額は上がりますが、支援内容や職場定着までの手厚いフォローを考えると、長期的に見て高い費用対効果が期待できるサービスです。
利用料以外にかかる費用
就労移行支援のサービス自体は、多くの方が無料または低額で利用できますが、それ以外にも必要となる費用があることを知っておきましょう。
まず挙げられるのが、事業所までの交通費です。通所にかかる電車やバスの運賃は原則自己負担となりますが、自治体や事業所によっては補助制度がある場合もありますので、確認しておくと安心です。
また実習先企業や就職面接に行く際の交通費も自費で負担するケースが多くなっています。これに加えて、通所中の昼食代や、資格取得を目指す場合の受験料・教材費なども必要になることがあります。
「お金がないけど利用したい」場合の対処方法
就労移行支援を利用したいけれど、経済的な事情からためらっている方もいるでしょう。しかし、実は「お金がない」状況でも利用を後押ししてくれる制度がいくつもあります。
ここでは、代表的な制度について紹介します。
失業保険
失業保険(雇用保険の基本手当)は、これまで雇用保険に加入して働いていた人が離職した際に、再就職までの生活を支える目的で支給される手当です。
就労移行支援に通いながらでも受給できる場合があり、障がいのある方は「就職困難者」に認定され、支給期間が通常よりも長くなる(150~360日間)可能性があります。
なお、支給金額は、離職前の給与額に基づいて決定されます。
傷病手当金
傷病手当金は、企業などの健康保険に加入している方が、病気やけがで働けなくなったときに支給される給付制度です(※国民健康保険には適用されません)。
一定の条件を満たせば「労務不能」や「療養中」と認められる期間に、就労移行支援に通いながら受給できる場合もあります。支給額は、休職前の給与の3分の2で、最長で1年半まで受給可能です。
ただし、失業保険との併用はできないため、自分の状況に合った制度を選びましょう。
自立支援医療制度
自立支援医療制度は、障がいのある方が必要な医療を継続的に受けられるよう、医療費の自己負担を軽減する制度です。通常3割負担の医療費が1割に、あるいは所得に応じて設定された負担上限額となります。
精神疾患(うつ病や統合失調症、パニック障がいなど)のある方にとっては、通院時の診察料や薬代、デイケアの利用料も対象となるため、継続的な治療と就労準備を両立させたい場合に役立つ支援です。
生活福祉資金
生活福祉資金貸付制度は、経済的に困窮している低所得世帯や障がい者世帯、高齢者世帯を対象に、安定した生活を送るための資金を貸し付ける制度です。実施主体は都道府県の社会福祉協議会で、生活に関する相談支援と併せて利用できます。
貸付の種類には「総合支援資金(生活再建のための費用)」や「福祉資金」などがあり、目的に応じて柔軟に選択できます。
障がい年金
障がい年金は、病気やけがが原因で生活や就労に制限がある人に対して支給される公的年金制度です。「障がい基礎年金(国民年金加入者向け)」と「障がい厚生年金(厚生年金加入者向け)」の2種類があり、障がいの程度に応じて受給額が決まります。
就労移行支援に通っている期間も受給可能で、継続的な生活支援として活用できるのが特徴です。また障がい者手帳を持っていなくても申請できるため、「対象かどうか分からない」と感じる方も、一度相談してみることをおすすめします。
家族からの援助・貯蓄
就労移行支援の利用期間中は、基本的にアルバイトなどの収入が得られないため、家族からの経済的援助を受けている方も多くいます。
例えば、実家で生活費をかけずに暮らしたり、仕送りを受けたりすることで、金銭的な負担を減らすことが可能です。
このような支援を受けるためには、「就労移行支援は就職の準備をする場所であり、通所中は原則として収入を得ることが難しい」という点を、家族に丁寧に説明することが大切です。
生活保護
生活保護は、病気や障がいなどによって収入が得られず、日常生活を送ることが難しい人を対象に、国が最低限度の生活を保障する制度です。生活保護を受給しながら就労移行支援を利用できます。
支給される内容は、生活費(食費・衣類・日用品費)、住宅扶助(家賃)、医療費、光熱費などさまざまです。地域や世帯構成によって支給額は異なりますが、障がい者手帳を所持している場合には「障がい者加算」が適用され、支給額が上乗せされるケースもあります。
また就労移行支援事業所までの交通費についても、必要性が認められれば「交通費」として加算されます。生活保護の申請について不安や疑問がある場合は、事前に相談員へ相談しましょう。
就労移行支援を受けている間にアルバイトはできる?
基本的に、就労移行支援を受けている期間中はアルバイトやパートなどの就労は原則として禁止されています。これは、就労移行支援が「働いていない障がい者」を対象に、就職に向けた準備や訓練を行う制度であるためです。
すでに就労していると見なされると、「支援の必要がない」と判断され、サービスの対象外となってしまう可能性があります。
ただし、例外的にアルバイトが許可されるケースもあります。いずれにしても、アルバイトを希望する場合は、事前に事業所や自治体に相談し、ルールに沿った対応を取ることが大切です。
お金に関して相談できる窓口
就労移行支援の利用にあたって、費用面に不安を感じる方は少なくありません。負担を一人で抱え込まず、制度に詳しい公的窓口に早めに相談することが大切です。ここでは、就労移行支援の費用や減免制度について相談できる代表的な窓口をまとめました。
| 窓口名 | 主な相談内容 | 所在・連絡先の目安 |
| 福祉事務所 | 就労移行支援の利用手続き、減免制度、生活保護制度との関係など | 市役所・区役所内に設置 |
| 障がい福祉窓口 | 障害者総合支援法に基づく福祉サービス全般、利用料の有無など | 各自治体の障がい福祉課等 |
| 生活保護課 | 就労移行支援の利用中に生活保護を受けられるかどうかなど | 自治体の福祉担当窓口 |
| 行政相談窓口(総務省) | 各種行政手続きに関する相談や制度の問い合わせ | 全国の行政相談センター等 |
| 障害者就業・生活支援センター | 収入・生活の不安、就職活動、支援制度全般に関する相談 | ハローワークと連携あり/地域ごとに設置 |
| 自立相談支援機関 | 経済的な困窮に対する総合支援、就労・住居・生活全般の相談 | 各市町村に設置(生活困窮者自立支援法) |
こうした窓口では、利用者の状況に応じた助言や手続きのサポートが受けられます。
費用の減免制度が適用されるかどうかや、他の支援制度と併用できるかといった具体的な相談も可能です。制度の内容は自治体によって異なる場合もあるため、まずはお住まいの市役所や町村役場での確認をおすすめします。
まとめ
就労移行支援は、就職を目指す障がいのある方にとって心強い支援制度です。利用料は多くの方が無料もしくは低額で済み、経済的な負担を気にせずに利用できる環境が整っています。
「お金がないから無理かもしれない」と諦める前に、公的制度や支援機関に相談してみることが大切です。失業保険や障がい年金、自立支援医療制度など、状況に応じて使える制度は数多くあります。まずは気軽な相談や見学から始めて、自分に合った支援を探してみましょう。
就労移行支援事業所「ココルポート」では、うつ病や発達障がいなどがある方に向けて、パソコンスキルの習得や履歴書添削、職場実習などを通じた就職サポートを提供しています。
「どんな仕事が向いているか分からない」「働き続けられるか不安」という方も、自分のペースで一歩ずつ前に進めるよう支援しています。興味のある方は、ぜひ一度相談してみてください。
こんなお困りありませんか?
以下はよくご相談いただく課題やお悩みの例になります。
ご自身にあてはまる課題やお悩みをクリックするとご提案の例が表示されますのでぜひご参考にしていただければと思います。
チャレンジすることに不安があるかもしれませんが、Cocorportは「失敗できる場」なので、ぜひいろいろなことにチャレンジしていただければと思います。
-
自己分析(理解)
-
対人コミュニケーション
-
体力・生活リズムストレス耐性
-
職場定着・相談先
-
就職活動・スキル
関連記事
関連アイテムはまだありません。
- お電話はこちら
- 0120-336-866
※お電話受付時間 9:00~18:00(日曜定休)

お気軽にお問合せください!
開催予定の就労移行支援の説明会情報
-
名古屋藤が丘駅前Office
Cocorport 名古屋藤が丘駅前Office見学会&就職個別相談会のお知らせ(参加無料) -
大船Office
大船Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料) -
川越第2Office
Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料)※プログラム体験会も開催中 -
目黒駅前Office
Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料) -
Cocorport Rework 大阪天王寺駅前
リワーク(復職支援)現地説明会&オンライン説明会(参加無料) -
Cocorport Rework 藤沢
リワーク(復職支援)現地説明会&オンライン説明会(参加無料) -
川越第3Office
Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料)※プログラム体験会も開催中 -
名古屋大曽根Office
Cocorport 名古屋大曽根Office Office見学会&就職個別相談会のお知らせ(参加無料) -
名古屋駅Office
Cocorport 名古屋駅Office Office見学会&就職個別相談会のお知らせ(参加無料) -
Cocorport Rework 松戸駅前
リワーク(復職支援)説明会&個別相談会(参加無料)
Officeブログ新着情報
-
北千住Office 2026/02/27
【プログラム内容&感想】花結びチャームづくり🌷 -
Cocorport Rework 大阪天王寺駅前 2026/02/27
スタッフ紹介⑤ -
横浜戸塚Office 2026/02/27
企業見学のポイント☆彡 -
横須賀第2Office 2026/02/27
横須賀第2Office 環境整備部 始動! -
新板橋駅前Office 2026/02/27
プログラム紹介【自己PRの作成】 -
新板橋駅前Office 2026/02/27
プログラム紹介【今日からできる時間管理術】 -
新板橋駅前Office 2026/02/27
プログラム紹介【メモ取り基本編】 -
名古屋藤が丘駅前Office 2026/02/27
🍑3月前半プログラム紹介🍑 -
南浦和駅前Office 2026/02/27
ココルポートでできること🪄 -
長津田駅前Office 2026/02/26
プログラム紹介 余暇「格付けチェック!!」