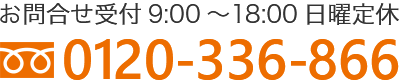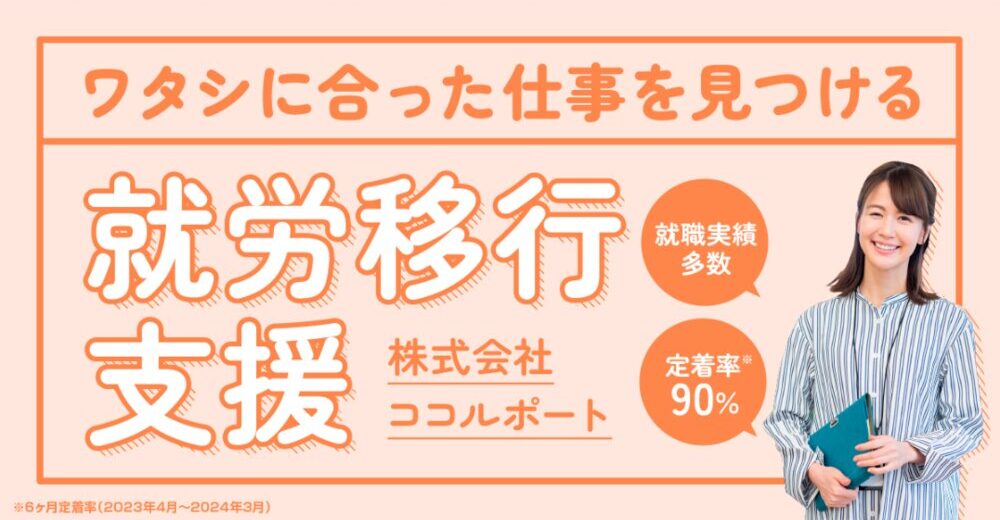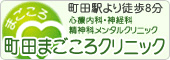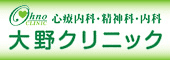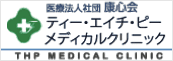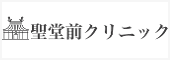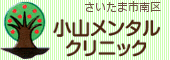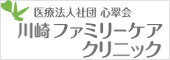- ココルポート(就労移行支援・定着支援/自立訓練/計画相談) HOME
- お役立ち情報
- 就労移行支援で就職できなかった人はいる?対策やポイントを解説
就労移行支援で就職できなかった人はいる?対策やポイントを解説
公開日:2025/10/02
更新日:2025/10/02

就労移行支援を利用したものの、就職に至らず「これからどうすればいいのだろう」「自分だけがうまくいかないのでは」と不安を感じている方は少なくありません。
就労移行支援を利用しても就職できないケースは実際にあるため、決して自分を責めないでください。本記事では、就労移行支援で就職できなかった人の割合や就職できなかったときの対策などについて詳しく解説します。
目次
就労移行支援で就職できなかった人はいる?【データで見る実態】

「就労移行支援を利用したのに就職できなかったのは自分だけではないか」と不安になる方も少なくありません。しかし、実際にはそうしたケースは決して珍しくありません。
厚生労働省の令和5年の調査によると、全国の就労移行支援事業所の就職率は58.8%と報告されています。およそ4割の利用者が就職に至っていない、または就職以外の進路を選んでいるというのが現実です。
就職支援を受けてもすぐに就職できない人は多く、そこにはさまざまな事情や背景があります。まずは「就職できなかったのは特別なことではない」と捉え、焦らず今後の選択肢を見つけていくことが大切です。
※出典: 厚生労働省 .「就労支援施策の対象となる障害者数/地域の流れ」.
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001379219.pdf ,(2025-08-05).
就労移行支援で就職できなかった人の理由
就労移行支援を利用しても、全ての人が必ず就職できるとは限りません。実際には、さまざまな要因が重なり、就職に至らないケースもあります。ここでは、就労移行支援で就職できなかった主な理由について解説します。
就労移行支援事業所とのミスマッチ
就職に結びつかなかった原因の一つに、事業所とのミスマッチがあるかもしれません。利用者の希望や障がいの特性に対し、事業所が提供する支援内容や専門性が合っていないと、十分な成果を得るのが難しくなるケースがあります。
例えば、対人関係に苦手意識があり、ITスキルを身につけて苦手なコミュニケーションを避ける働き方を目指す場合に、希望する訓練がなかったりすると、通所が負担に感じられることがあります。
大切なのは、「何が自分に合うか」を事前に見極めることです。事業所選びの際には、訓練内容や専門性だけでなく、スタッフや利用者の雰囲気、支援の進め方などをしっかり確認することが重要です。
体調や生活リズムの不安定さ
日によって体調が大きく変動したり、生活リズムが整わず朝起きられなかったりすることは、就職活動において大きなハードルになります。例えば、午前中に強い眠気が残り通所が難しい、天候や気圧の変化で体調が崩れやすいといったケースは珍しくありません。
就労移行支援の通所頻度が極端に少なかったり、週に何度も遅刻や欠席が続いたりすると、企業から「仕事も継続できないのではないか」と懸念され、採用に慎重になる可能性があります。
通所状況は、就職後も無理なく勤務を続けられるかどうかの判断材料の一つです。
自己理解の不足
自分の障がいや病気の特性を正しく理解していない場合、面接や職場で適切な自己説明ができず、不採用につながるケースがあります。「どのような配慮があれば働けるのか」「苦手なことにどう対応しているのか」といった点を明確に伝えることは、企業に安心感を与える上でも重要です。
自己理解が浅いと、周囲とのすれ違いや誤解を招きやすく、環境への適応能力に難があると判断される可能性があります。
就職活動への姿勢と準備不足
就職先に対する理想が高過ぎる場合、応募できる企業の選択肢が限られ、結果として不採用が続いてしまうことがあります。
「正社員」「高給与」「賞与あり」など、条件にこだわり過ぎることで競争率の高い求人に集中し、なかなか採用に至らないというパターンも少なくありません。
またスキルの習得に時間をかけ過ぎてしまい、実際の就職活動や応募準備が後回しになると、チャンスを逃すことにもつながります。
コミュニケーション能力の課題
職場では、専門的な会話よりも「最低限のやり取り」ができることが重視されます。例えば、出勤時の挨拶ができない、話しかけられても無言になってしまう、不明点があっても質問できないといったケースでは、周囲との連携が難しくなり、ミスやトラブルにつながる恐れがあります。
また「報告・連絡・相談(ホウレンソウ)」ができないと、体調不良や業務の遅れに気付かれず、かえって本人の負担が大きくなってしまいかねません。感情のコントロールが苦手で、注意を受けた際に混乱してしまうケースも注意が必要です。
企業は「一緒に働けるかどうか」を重視するため、特別なスキルよりも、社会人として「最低限のやり取り」ができるかが問われます。
就労移行支援を利用して就職できなかったらどうする?

就労移行支援を利用しても、すぐに就職できるとは限りません。思うような結果が出なかったときこそ、自分に合った次のステップを考えることが大切です。ここでは、就職に至らなかった場合に取れる対応策を紹介します。
就労移行支援の利用期間を延長する
就労移行支援の利用期間は、原則として2年間と定められていますが、「体調不良で継続的な訓練が困難だった」「途中で入院していた」「訓練の進捗が遅れており就職準備が整っていない」といった正当な理由がある場合は、最大1年間の延長が認められることがあります。
延長を希望する場合は、現在利用している就労移行支援事業所の支援員と相談の上、支援計画の見直しや延長理由の整理を行い、市区町村の障がい福祉窓口に申請します。
就職に向けた準備期間を設ける
支援期間中に無理をして体調やメンタルに支障を来してしまった場合は、一度しっかりと休養を取ることも重要です。
焦って次のステップに進むよりも、まずは生活リズムや健康状態を整えることで、就職に向けた準備をより確かなものにできます。
医療機関や支援機関と連携しながら、自分にとって適切なペースで再スタートを切ることが大切です。
就労移行支援事業所を移る
現在利用している事業所が、自分の目指す方向性やニーズに合っていないと感じた場合は、他の事業所への変更を検討するのも一つの方法です。事業所によって支援の内容や得意とする分野、スタッフの雰囲気は異なるため、見学や体験利用を通じて、自分に合った場所を探すことが大切です。
適切な環境に出会うことで、就職に向けた準備やモチベーションが大きく変わることもあります。
就労継続支援(A型・B型)へ移行する
一般企業への就職が難しいと感じる場合は、就労継続支援への移行を検討するのも方法の一つです。A型は雇用契約を結んで働きながら支援を受けられる制度で、一定の労働能力がある方向けです。
一方、B型はより支援の手厚い非雇用型で、体力や精神面でフルタイム勤務が難しい方も無理なく作業を行える環境が整っています。
どちらも「働くこと」に慣れるために活用でき、将来的に一般就労を目指す上で役立ちます。
障害者就業・生活支援センターの利用
障害者就業・生活支援センターは、障がいのある方が安定して働き続けるために、就労と生活の両面から支援してくれる公的機関です。障がい者手帳を持っていない方も相談できます。
支援内容は多岐にわたり、「働きたいけれど自分に向いている仕事が分からない」「履歴書の書き方が不安」「仕事を始めたいが生活リズムが整わない」といった悩みに対し、専門スタッフが一緒に課題を整理しながら解決策を考えてくれます。
ハローワークと連携した求人紹介、企業見学の調整、職場定着のためのフォローなど、就職後まで視野に入れた支援を受けられるのも特徴です。
ハローワークを利用する
ハローワークは、離職者や求職中の方を対象に、無料で受けられる就職支援や職業訓練を提供している公的な就業支援機関です。
ITスキルや事務作業、介護技術、製造業の基礎など、幅広い分野の職業訓練講座が用意されており、「働くために何かを学び直したい」と考えている方にとって、大きなメリットがあります。
障がいのある方専用の「専門援助窓口」では、福祉職や就労支援の経験を持つ担当者が、個別の事情に応じて丁寧に対応してくれます。「どんな仕事が向いているか分からない」「ブランクが不安」「面接がうまくいかない」といった悩みに対して、自己分析の手伝いや応募書類の添削、模擬面接の実施など、実践的なサポートが受けられるのが特徴です。
また職業訓練を受けながら求職活動を続けることで、スキルアップと就職準備を並行して進められる点も大きなメリットです。
就職エージェントを利用する
障がい者の就職支援に特化した就職エージェントでは、企業とのマッチングに特化した支援が受けられ、担当アドバイザーがつくのが大きな特徴です。
アドバイザーは、利用者の障がい特性や得意・不得意、希望する働き方(週何日働きたいか、どのような配慮が必要か)などを丁寧にヒアリングし、それに合った求人を紹介してくれます。
さらに、就職が決まった後も、職場への配慮事項の伝達や勤務後のフォローなど「職場に定着するまで」の支援を継続して行ってくれるため、働き始めてからの不安も軽減されます。
就労移行支援を利用して就職を成功させるためには?
就労移行支援を最大限に活用することで、就職の可能性を高めることができます。ただし、支援を受けるだけではなく、「どのように利用するか」が就職の成否を左右します。
ここでは、就職を成功させるために意識したい3つのポイントを見ていきましょう。
自分に合った就労移行支援事業所を選択する
事業所選びは、就職支援の質や自分自身の成長に大きく影響します。自宅から通いやすい距離にあるかどうかだけではなく、カリキュラムの内容や、スタッフ・利用者の雰囲気なども重要な判断材料です。
可能であれば複数の事業所を見学し、体験利用を通じて比較検討することをおすすめします。
「通いやすさ」だけで選ぶのではなく、自分のニーズや就職目標に合った支援を受けられるかどうかを確認しましょう。
就職に必要なスキルを習得・実践する
希望する職種に必要なスキルを身に付けることは、就職活動において大きなアピールポイントです。例えば、事務職を目指すならWordやExcelの基本操作、介護職なら移乗や食事介助の技術、IT系であればタイピングやプログラミングの基礎など、目標に応じた実践的なスキル習得が求められます。
就労移行支援では、こうした訓練に加えて、企業実習の機会が用意されていることもあります。実際の職場で数日〜数週間働くことで、「どんな仕事が自分に合っているか」「どこに課題があるか」を体感的に理解でき、就職後のミスマッチ防止にも役立ちます。
自己理解を深める
自分の障がいや病気について理解を深め、「どのような環境やサポートがあれば安心して働けるか」を整理することは、就職活動において大切です。企業は、障がいの内容そのものよりも、「本人が自分の特性を把握し、必要な配慮を自分で説明できるか」を重視する傾向があります。
例えば、「複数の作業を同時に行うと混乱しやすい」「急な予定変更が苦手」といった特性がある場合には、「メモを小まめに取る」「スケジュールをあらかじめ提示してもらう」などの対処法も併せて伝えることで、企業側に安心感を与えられるでしょう。
このような自己理解は、応募書類の志望動機や面接での自己PRにもつながります。「自分はどんな環境で力を発揮できるか」「どのようなサポートがあれば継続して働けるか」を言語化できるようになると、採用担当者にも前向きな印象を与えられるでしょう。
就労移行支援に関するQ&A
ここでは、就労移行支援に関して多くの方が感じる疑問や不安について、Q&A形式で分かりやすく解説します。
Q1. 就労移行支援を利用しながら就労できる?
原則として、就労移行支援は「働いていない方」を対象とした支援制度です。すでにアルバイトやパートなどで働いている場合は、利用の対象外と判断されることがあります。
ただし、休職中で職場復帰を目指している場合など、一定の条件を満たすケースでは、就労移行支援の利用が認められる可能性もあります。
判断は自治体や事業所によって異なるため、具体的な状況を就労移行支援事業所に直接相談するのがおすすめです。
Q2. 就労移行支援を利用した後のサポートはある?
はい、あります。就職後も支援が継続されるのが、就労移行支援の特徴の一つです。支援員が就職後の職場での悩みや困りごとについて相談に応じ、必要に応じて企業と連携を図ります。
例えば、利用者本人と企業、事業所の三者による面談を行い、業務や人間関係の課題を共有しながら、働きやすい環境を整えていくことが可能です。
まとめ
就労移行支援を利用しても、就職できないことは決して珍しいことではありません。体調やスキル、支援内容とのミスマッチなど、人によって背景はさまざまです。大切なのは、自分を責めるのではなく、原因を客観的に見直し、自分に合った次のステップを考えることです。
支援の延長や事業所の変更、就職エージェントや公的機関の活用など、選択肢は一つではありません。焦らず、自分のペースで進めることが、就職への近道になる場合もあります。
もし「次に何をすればいいのか分からない」と迷っているなら、専門家の力を借りてみるのも方法の一つです。
就労移行支援事業所「ココルポート」では、うつ病・発達障がい・適応障がいなど精神的な不安がある方に向けて、個々の状況に応じたオーダーメイドの就職支援を行っています。
「働きたいけれど自信がない」「もう一度チャレンジしたい」という方は、ぜひ一度ココルポートにご相談ください。
こんなお困りありませんか?
以下はよくご相談いただく課題やお悩みの例になります。
ご自身にあてはまる課題やお悩みをクリックするとご提案の例が表示されますのでぜひご参考にしていただければと思います。
チャレンジすることに不安があるかもしれませんが、Cocorportは「失敗できる場」なので、ぜひいろいろなことにチャレンジしていただければと思います。
-
自己分析(理解)
-
対人コミュニケーション
-
体力・生活リズムストレス耐性
-
職場定着・相談先
-
就職活動・スキル
関連記事
関連アイテムはまだありません。
- お電話はこちら
- 0120-336-866
※お電話受付時間 9:00~18:00(日曜定休)

お気軽にお問合せください!
開催予定の就労移行支援の説明会情報
-
名古屋藤が丘駅前Office
Cocorport 名古屋藤が丘駅前Office見学会&就職個別相談会のお知らせ(参加無料) -
大船Office
大船Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料) -
川越第2Office
Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料)※プログラム体験会も開催中 -
目黒駅前Office
Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料) -
Cocorport Rework 大阪天王寺駅前
リワーク(復職支援)現地説明会&オンライン説明会(参加無料) -
Cocorport Rework 藤沢
リワーク(復職支援)現地説明会&オンライン説明会(参加無料) -
川越第3Office
Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料)※プログラム体験会も開催中 -
名古屋大曽根Office
Cocorport 名古屋大曽根Office Office見学会&就職個別相談会のお知らせ(参加無料) -
名古屋駅Office
Cocorport 名古屋駅Office Office見学会&就職個別相談会のお知らせ(参加無料) -
Cocorport Rework 松戸駅前
リワーク(復職支援)説明会&個別相談会(参加無料)
Officeブログ新着情報
-
北千住Office 2026/02/27
【プログラム内容&感想】花結びチャームづくり🌷 -
Cocorport Rework 大阪天王寺駅前 2026/02/27
スタッフ紹介⑤ -
横浜戸塚Office 2026/02/27
企業見学のポイント☆彡 -
横須賀第2Office 2026/02/27
横須賀第2Office 環境整備部 始動! -
新板橋駅前Office 2026/02/27
プログラム紹介【自己PRの作成】 -
新板橋駅前Office 2026/02/27
プログラム紹介【今日からできる時間管理術】 -
新板橋駅前Office 2026/02/27
プログラム紹介【メモ取り基本編】 -
名古屋藤が丘駅前Office 2026/02/27
🍑3月前半プログラム紹介🍑 -
南浦和駅前Office 2026/02/27
ココルポートでできること🪄 -
長津田駅前Office 2026/02/26
プログラム紹介 余暇「格付けチェック!!」