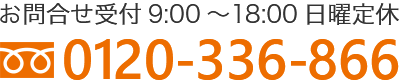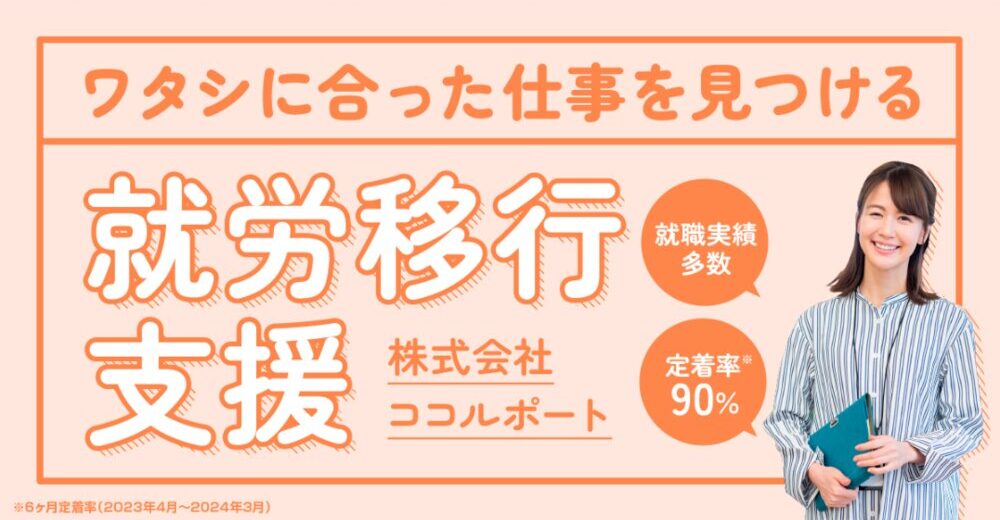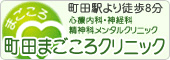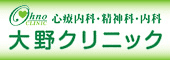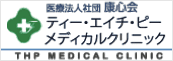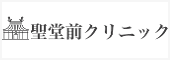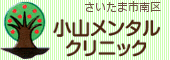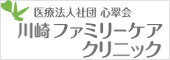- ココルポート(就労移行支援・定着支援/自立訓練/計画相談) HOME
- お役立ち情報
- 指定難病と障がい者手帳|取得条件・メリット・申請方法を徹説
指定難病と障がい者手帳|取得条件・メリット・申請方法を徹説
公開日:2025/05/12
更新日:2025/05/12

指定難病と診断されると、長期的な治療や通院が必要となり、医療費や生活面での負担が大きくなることがあります。しかし、障がい者手帳を取得することで、医療費助成や税制の優遇、就労支援など、さまざまな支援を受けることが可能です。
本記事では「難病」と「指定難病」の違いをはじめ、障がい者手帳の種類、取得条件、手続きの流れ、取得後のメリット、さらには難病患者を支える公的制度についても詳しく解説します。
目次
難病・指定難病とは
難病とは、発症の原因がまだ明らかになっておらず、根本的な治療法が確立されていないために、長期間にわたる療養を必要とする病気のことです。症状の出方や進行の仕方は個人差が大きく、日常生活への影響もさまざまです。
難病には、潰瘍性大腸炎や全身性エリテマトーデス、多発性硬化症、重症筋無力症などがあります。
2015年に施行された「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」では、以下の4つの条件を全て満たすものが「難病」と定義されています。
- ・発病の仕組み(病因)が不明であること
- ・有効な治療法が確立されていないこと
- ・患者数が少なく(希少性)、個別の支援制度が整っていないこと
- ・長期間の療養が必要であること
難病のうち、医療費助成など公的支援の対象として国が指定しているものを「指定難病」と呼びます。指定難病は、以下のような追加条件を満たした疾病です。
- ・日本国内の患者数が人口のおおむね0.1%程度にとどまること
- ・客観的な診断基準や指標が確立されていること
厚生労働大臣が専門家の意見を元に「指定難病」として定めます。2025年4月時点で、指定難病の数は348疾病です。
※参考:厚生労働省.「指定難病」.
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000084783.html ,(参照 2025-04-08).
障がい者手帳の基礎知識

障がい者手帳とは、障がいのある方が必要な支援やサービスを受けやすくするために交付される手帳の総称で、「身体障がい者手帳」「療育手帳」「精神障がい者保健福祉手帳」の3種類があります。
身体障がい者手帳は、視覚や聴覚、肢体不自由など体の一部に障がいがある方に交付される手帳です。「身体障害者福祉法」に基づき、医師の診断書や意見書を元に、各都道府県や指定都市、中核市が判定を行います。
療育手帳は、知的障がいのある方に交付される手帳で、児童相談所または知的障がい者更生相談所にて知的障がいの程度が判定されます。
精神障がい者保健福祉手帳は、統合失調症やうつ病、発達障がいなど精神疾患により日常生活に支障があると認められた方に交付される手帳です。精神疾患の状態と、日常生活における能力の障がい度に応じて、1級から3級までに分かれています。
指定難病患者は障がい者手帳を取得できる
指定難病患者は障がい者手帳を取得できる場合があります。ここからは、障がい者手帳について詳しく見ていきましょう。
指定難病患者が取得できる障がい者手帳
指定難病の多くは体の機能に関わる障がいを伴うことが多いため、対象者の多くは「身体障がい者手帳」の交付を受けています。厚生労働省の調査によれば、難病と診断された方のうち約56%が障がい者手帳を所持しており、その半数以上が身体障がい者手帳です。
一方で、難病と診断されながらも、障がい者手帳を取得していない方が約4割存在するのも事実です。その理由には、「症状が安定しているため対象に該当しない」「障がい等級に達していない」「手続きの煩雑さや制度の周知不足」などが挙げられます。
手帳がないことで医療費助成や福祉制度を利用できないケースもあるため、対象の可能性がある方は、早めに医師や自治体の窓口に相談し、取得の可否を確認することが重要です。
※出典:厚生労働省.「障害者雇用率制度・納付金制度について関係資料」.
https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/000772377.pdf ,(参照 2025-04-08).
障がい者手帳を取得するメリット

障がい者手帳を取得することで、医療費や税制上の優遇措置をはじめとする多くの支援を受けることが可能になります。手帳の種類や等級によって利用できる制度は異なりますが、等級が高いほど支援の幅は広がります。ここでは、障がい者手帳を持つことで得られる主なメリットについて解説します。
医療費助成
障がい者手帳を所持していることで、各自治体が実施する医療費助成制度の対象となる場合があります。例えば、通院や入院時の自己負担額が軽減される他、薬代や検査費用の一部が補助されます。
助成の内容は自治体によって異なるため、詳細はお住まいの地域の福祉窓口で確認しましょう。
税金の控除・減免
障がい者手帳を所持している方は、所得税や住民税において「障がい者控除」を受けることができます。一般障がい者の場合、所得から27万円、特別障がい者に該当する場合は40万円、同居特別障がい者は75万円が控除されます。
相続税については、障がい者が相続人となる場合に「障がい者控除」が適用され、85歳までの年数ごとに1年につき10万円が軽減されます(特別障がい者は1年につき20万円)。
また自動車税・軽自動車税の減免制度もあり、障がい者本人が通院や通勤、通学に利用する自動車については、税金が全額または一部免除される場合があります。
さらに、預貯金の利子にかかる税金を非課税にできる「マル優」制度も利用可能です。年間350万円までの預貯金に対する利子が非課税となります。
このように、障がい者手帳を持つことで、さまざまな税制上の優遇措置を受けることが可能です。
※出典:国税庁.「No.1160 障害者控除」.
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm ,(参照 2025-04-08).
※出典:国税庁.「No.4167 障害者の税額控除」.
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4167.htm ,(参照 2025-04-08).
※出典:一般社団法人全国銀行協会.「障がい者や遺族年金受給者などの非課税貯蓄「マル優・特別マル優」」.https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-b/3764/ ,(参照 2024-04-08).
さまざまなサービスの割引
障がい者手帳を提示することで、公共交通機関の運賃割引をはじめ、生活に関わるさまざまなサービスで優遇を受けられます。例えば、電車やバス、タクシーの割引、ETCや高速道路料金の減免、NHK受信料の免除、美術館・博物館などの公共施設の入館料割引などがあります。付き添いの家族にも適用されるケースがあるのも特徴です。
就労支援
障がい者手帳を所持していると、障がい者雇用枠での就職活動が可能になり、特別な配慮の元で働ける機会が広がります。ハローワークや自治体の就労支援センターでは、履歴書の書き方や職場体験、面接対策などの支援を受けられる他、職場定着に向けたフォローアップも充実しています。
障がい者手帳の申請方法
指定難病の方が取得することが多い身体障がい者手帳の申請方法と必要書類について解説します。なお、詳しい手続きや条件は自治体によって異なるため、お住まいの市区町村の福祉担当窓口に確認することが大切です。
必要書類一覧
身体障がい者手帳を申請する際には、以下の書類を準備する必要があります。
- ・身体障がい者診断書・意見書(指定医師が記入)
- ・本人の写真(縦4cm×横3cm、上半身、脱帽。デジタルカメラでの撮影可、写真用紙に印刷)
- ・交付申請書(マイナンバーの記載が必要)
診断書・意見書の作成について
身体障がい者診断書・意見書は、厚生労働大臣が定めた「身体障がい者福祉法第15条指定医」によって作成される必要があります。指定医の一覧や相談先は、お住まいの市区町村または町村部の福祉事務所で確認できます。
東京都では、「心身障がい者福祉センター」が障がい別に診断書のフォーマットを公開しています。
東京都心身障害者福祉センター「身体障害者手帳診断書・意見書」
審査の流れと期間
提出された診断書を元に、各自治体が障がいの程度や等級を審査します。申請から手帳の交付までには、通常1カ月程度かかるとされています。
ただし、以下のようなケースでは審査が長引くこともあります。
- ・診断書の記載内容について指定医に確認が必要な場合
- ・身体障がい者福祉法の対象に該当するか判断が難しい場合
東京都では、身体障がい者福祉法別表に該当しない場合と、等級認定において専門的な審査が必要とされた場合は、年4回ある東京都社会福祉審議会に諮問されます。
認定後に必要な手続き
審査が完了し、障がい者手帳の交付が決定すると、郵送などで承認通知が届きます。その後、自治体の福祉窓口にて手帳を受け取り、手続きは完了します。
なお、手帳を紛失した場合や破損した場合には、再交付の申請が可能です。
指定難病患者が障がい者手帳を取得する際の注意点
指定難病と診断された方が障がい者手帳を取得する場合、申請後に多くの支援を受けられる一方で、手帳の維持や取り扱いに関して注意すべき点もいくつかあります。ここでは、障がい者手帳の運用上の注意点について解説します。
障がい者手帳は更新手続きが必要
身体障がい者手帳に有効期限は設けられていませんが、症状の悪化や新たな障がいの発生により、等級変更や障がい項目の追加が必要になった際は、改めて医師の診断書を提出し、再度審査を受ける必要があります。
また東京都では「再認定制度」が導入されており、特定の障がいについては改めて審査を受けることを求められるケースもあります。
さらに、住所や氏名が変更になった際も、速やかにお住まいの市区町村の障がい福祉担当窓口へ届け出る必要があります。情報が更新されていないと、各種サービスや支援制度の利用に支障が出ることもあるため注意が必要です。
障がい者手帳の返還が必要となるケースがある
障がい者手帳は、常に障がいの状態を証明するものとして扱われます。そのため、障がいの状態が改善し、身体障がい者福祉法に定める基準を満たさなくなった場合や、ご本人が亡くなられた場合には、速やかに手帳を返還する必要があります。
指定難病患者の社会参加を支える制度とサービス
指定難病のある方が社会で自立し、安心して暮らしていくために、障がい者手帳以外にも多くの支援制度やサービスが整備されています。ここでは、医療・福祉・生活面など多方面から指定難病患者を支える制度について紹介します。
難病医療費助成制度
難病医療費助成制度は、指定難病患者の医療費負担を軽減するために設けられた公的制度です。重症度が一定以上と認定された場合、または軽症であっても医療費が高額となる場合には、自己負担額に上限が設けられます。所得区分に応じて負担額が決まるため、経済的に不安を抱える方も安心して治療を継続しやすくなります。
自己負担額については下記の通りです。
| 階層区分 | 階層区分の基準(※) | 自己負担上限額(月額)|外来+入院(患者負担割合:2割) |
| 一般 | ||
| 生活保護 | ― | 0円 |
| 低所得 I | 本人年収 〜80万円、市町村民税非課税(世帯) | 2,500円 |
| 低所得 II | 本人年収 80万円超、市町村民税非課税(世帯) | 5,000円 |
| 一般所得 I | 市町村民税課税以上7.1万円未満(年収約160〜370万円) | 10,000円 |
| 一般所得 II | 市町村民税7.1万円以上25.1万円未満(年収約370〜810万円) | 20,000円 |
| 上位所得 | 市町村民税25.1万円以上(年収約810万円〜) | 30,000円 |
また、高額かつ長期の場合や人工呼吸器等装着者などで条件が異なります。
※参考:難病情報センター.「指定難病患者への医療費助成制度のご案内」.
https://www.nanbyou.or.jp/entry/5460 ,(参照 2025-04-08).
障がい年金
障がい年金は、指定難病によって日常生活や仕事に支障を来すようになった方が、一定の条件を満たすことで受給できる公的年金制度です。年齢に関係なく、現役世代の方でも受給対象となる点が特徴です。
障がい年金には「障がい基礎年金」と「障がい厚生年金」があり、初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた方には「障がい基礎年金」が、厚生年金に加入していた方には「障がい厚生年金」が支給されます。
また障がいの程度が軽い場合でも、「障がい手当金」(一時金)が支給されることもあります。
障がい等級は1級から3級まであり(障がい基礎年金は1級・2級)、日常生活や就労の制限度合い、身体機能の障がいの程度などを元に審査されます。
障がい福祉サービス
障がい福祉サービスは、指定難病による身体機能の低下や生活上の困難を抱える方が、適切な支援を受けるための制度です。居宅介護、重度訪問介護、自律訓練や就労移行支援、就労継続支援A型・B型などの多様なサービスがあります。
地域生活支援事業
地域生活支援事業は、指定難病患者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう支援する自治体主導の仕組みです。地域移行支援では、医療機関から地域生活への移行に必要な相談や付き添い支援が行われ、地域定着支援では1人暮らしなどを行う患者に対して見守りや緊急対応体制を提供しています。
難病相談支援センター
難病相談支援センターは、指定難病患者とその家族の悩みや不安に寄り添い、必要な情報や支援先を案内する相談窓口です。医療や生活支援、就労、福祉制度に関する相談に幅広く対応しており、専門の相談員が無料でサポートしています。
患者団体
患者団体は、指定難病患者やその家族が中心となって組織された団体で、同じ病気がある人同士が情報を共有し、支え合うための活動を行っています。疾患ごとの専門情報を発信する他、医療現場や行政との連携によって制度改善に向けた提言も行っており、社会的な影響力も持つ存在です。
まとめ
指定難病と診断されても、障がい者手帳を取得することで、医療費助成をはじめ、税制の優遇、交通費の割引、就労支援など、日常生活の中で活用できる支援制度は多岐にわたります。
「就労支援」は、病気と向き合いながら「働くこと」を目指す方が利用できます。自分らしいペースで社会とのつながりを築いていくためにも、安心して頼れる支援機関を選ぶことが大切です。
ココルポートは、就労移行支援や就労定着支援、自立訓練(生活訓練)、計画相談支援を提供する事業所です。全国に拠点を展開し、障がいや難病がある方の「働く力」を育むためのサポートを行っています。
利用者の得意・不得意を丁寧に把握した上で、個別支援計画を立て、訓練や就職活動、就職後の定着支援までを一貫してサポートしています。まずは見学・相談から始めてみませんか。
こんなお困りありませんか?
以下はよくご相談いただく課題やお悩みの例になります。
ご自身にあてはまる課題やお悩みをクリックするとご提案の例が表示されますのでぜひご参考にしていただければと思います。
チャレンジすることに不安があるかもしれませんが、Cocorportは「失敗できる場」なので、ぜひいろいろなことにチャレンジしていただければと思います。
-
自己分析(理解)
-
対人コミュニケーション
-
体力・生活リズムストレス耐性
-
職場定着・相談先
-
就職活動・スキル
- お電話はこちら
- 0120-336-866
※お電話受付時間 9:00~18:00(日曜定休)

お気軽にお問合せください!
開催予定の就労移行支援の説明会情報
-
名古屋藤が丘駅前Office
Cocorport 名古屋藤が丘駅前Office見学会&就職個別相談会のお知らせ(参加無料) -
大船Office
大船Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料) -
川越第2Office
Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料)※プログラム体験会も開催中 -
目黒駅前Office
Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料) -
Cocorport Rework 大阪天王寺駅前
リワーク(復職支援)現地説明会&オンライン説明会(参加無料) -
Cocorport Rework 藤沢
リワーク(復職支援)現地説明会&オンライン説明会(参加無料) -
川越第3Office
Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料)※プログラム体験会も開催中 -
名古屋大曽根Office
Cocorport 名古屋大曽根Office Office見学会&就職個別相談会のお知らせ(参加無料) -
名古屋駅Office
Cocorport 名古屋駅Office Office見学会&就職個別相談会のお知らせ(参加無料) -
Cocorport Rework 松戸駅前
リワーク(復職支援)説明会&個別相談会(参加無料)
Officeブログ新着情報
-
北千住Office 2026/02/27
【プログラム内容&感想】花結びチャームづくり🌷 -
Cocorport Rework 大阪天王寺駅前 2026/02/27
スタッフ紹介⑤ -
横浜戸塚Office 2026/02/27
企業見学のポイント☆彡 -
横須賀第2Office 2026/02/27
横須賀第2Office 環境整備部 始動! -
新板橋駅前Office 2026/02/27
プログラム紹介【自己PRの作成】 -
新板橋駅前Office 2026/02/27
プログラム紹介【今日からできる時間管理術】 -
新板橋駅前Office 2026/02/27
プログラム紹介【メモ取り基本編】 -
名古屋藤が丘駅前Office 2026/02/27
🍑3月前半プログラム紹介🍑 -
南浦和駅前Office 2026/02/27
ココルポートでできること🪄 -
長津田駅前Office 2026/02/26
プログラム紹介 余暇「格付けチェック!!」