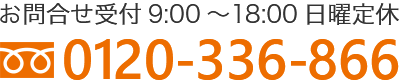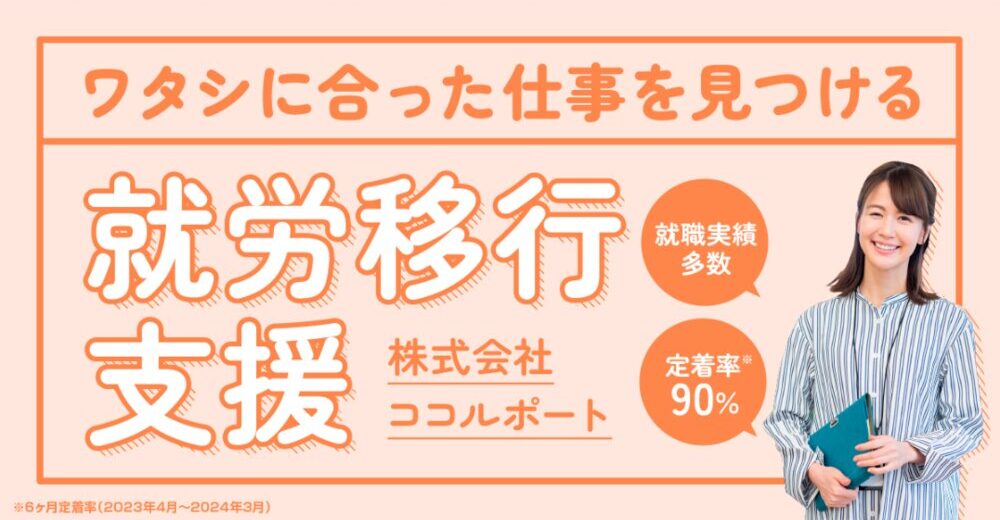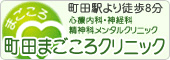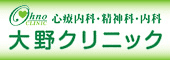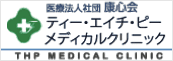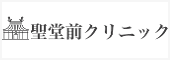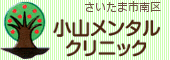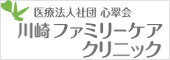- ココルポート(就労移行支援・定着支援/自立訓練/計画相談) HOME
- お役立ち情報
- 障がい者雇用から一般雇用への移行はできる? 後悔しないための転職活動の進め方
障がい者雇用から一般雇用への移行はできる? 後悔しないための転職活動の進め方
公開日:2025/11/03
更新日:2025/11/04

「障がい者雇用で経験を積んだけれど、一般雇用にも挑戦してみたい」「でも、失敗したら後悔しそうで不安……」と迷っている方もいるのではないでしょうか。確かに、雇用形態を移行することにはメリットとデメリットの両面があり、事前に正しく理解しておくことが大切です。
この記事では、障がい者雇用から一般雇用へ移行する際のメリットと注意点、移行を検討すべきタイミング、転職活動の進め方などについて紹介します。
目次
障がい者雇用から一般雇用への移行は可能

障がい者雇用から一般雇用へ移行することは可能です。実際に、一般雇用で働いていたものの体調を崩し、障がい者雇用に移行する人がいるように、その逆のケースも珍しくありません。
病状の改善や生活環境の変化により、障がい者手帳を更新できなくなると、障がい者雇用枠を継続できず、一般雇用への移行を余儀なくされることもあります。そのため、移行を見据えて準備を進めておくことが重要です。
障がい者雇用とは
障がい者雇用とは、心身に障がいのある人が、一般雇用とは別に設けられた「障がい者雇用枠」で企業や自治体に雇用される仕組みを指します。これは障がいを開示して働く「オープン就労」の一つであり、特性に合わせた配慮を受けながら働けるのが特徴です。
「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づいて、全ての事業主には従業員の一定割合以上の障がい者を雇用すること(=法定雇用率)が義務付けられています。対象となるのは、身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳のいずれかを所持している人です。
障がい者雇用は、働く機会を得やすくし、一人ひとりの特性に合わせた働き方を可能にするための大切な制度といえます。
一般雇用とは
一般雇用は、障がい者雇用枠以外の雇用形態を指し、障がいの有無にかかわらず同じ条件で採用・勤務する仕組みです。障がいのある方が一般雇用で働く場合には、自ら障がいを開示して勤務する「オープン就労」と、障がいを開示せずに勤務する「クローズ就労」の2つの選択肢があります。
事業者には、一般雇用においても合理的配慮を行う義務がありますが、障がい者雇用枠に比べると十分な配慮を受けにくいことが少なくありません。特にクローズ就労では障がいを開示していないため、必要な配慮を求めることが難しい点に注意が必要です。
障がい者雇用から一般雇用へ移行するメリット

障がい者雇用から一般雇用に移行することには、働き方や待遇の面でいくつかの大きなメリットがあります。ここでは主なメリットを紹介します。
キャリアアップの機会と仕事内容の幅が広がる
一般雇用では担当できる仕事の範囲が広く、企画や管理業務、リーダー業務など責任のある役割を任される可能性があります。例えば、障がい者雇用枠では補助的な業務が中心となることが多い一方、一般雇用に移行すると新規プロジェクトへの参加やチームのマネジメントなど、より幅広い経験を積めます。
また人事評価制度に基づき昇進や昇格のチャンスがあるため、努力次第でキャリアを段階的に積み上げられるのも大きな魅力です。
給与が高くなる可能性がある
フルタイム勤務や正社員として採用されやすい一般雇用では、障がい者雇用と比べて基本給や賞与が高く設定される傾向があります。例えば、同じ企業でも障がい者雇用枠では契約社員や短時間勤務での採用となり給与が抑えられる場合がありますが、一般雇用では正社員と同じ給与テーブルで処遇されるため、成果に応じて昇給や昇進も期待できます。
長期的に見ても、退職金制度や福利厚生の利用範囲が広がることで、総合的な待遇が改善されるケースが多いです。
一般社員との隔たりを感じにくい
障がい者雇用枠で働いていると、周囲の社員との業務範囲や立場の違いから「自分は特別枠で働いている」という意識を持ってしまい、職場になじみにくいと感じることがあります。一般雇用へ移行することで、他の社員と同じ評価基準や条件で働くことになり、職場の一員として認められている感覚を得やすくなります。結果として、同僚とのコミュニケーションが円滑になり、チームの一体感を味わいやすくなる点も大きなメリットです。
障がい者雇用から一般雇用へ移行するデメリット・注意点
障がい者雇用から一般雇用へ移行することで得られるメリットは大きい一方で、注意しておきたい点もあります。サポート体制の違いや求められる業務水準の高さによって、思わぬ負担を感じることもあるため、あらかじめ理解しておくことが大切です。障がい者雇用から一般雇用へ移行するデメリット・注意点について詳しく見ていきましょう。
合理的配慮やサポートが受けにくい
障がい者雇用では、体調や特性に応じた勤務時間の調整や作業内容の配慮など、制度に基づくサポートが用意されています。しかし一般雇用では、他の社員と同じ条件で働くことが前提となるため、こうした配慮が十分に受けられない場合があるのがデメリットです。その結果、体調不良や業務の不適合が原因で短期離職につながるリスクもあります。
業務上の負担や責任が増加する
一般雇用では、障がいの有無にかかわらず、他の社員と同じ基準で成果を求められるため、業務の負担が大きくなりやすい傾向があります。任される仕事の幅が広がる分、個人の裁量が増える一方で、納期管理や成果への責任も重くのしかかるでしょう。
さらに、チームリーダーや後輩指導といった役割を求められることもあり、これまで以上にプレッシャーを感じやすくなる可能性があります。こうした負担がストレスにつながるケースもあるため、自分の体調や働き方に見合った環境を慎重に選ぶことが大切です。
障がい者雇用からの移行を検討したいタイミング
障がい者雇用から一般雇用に移行するかどうかは、体調や働き方の希望、将来の目標などによって判断が分かれます。無理のない働き方を続けながらも、より安定した生活やキャリアアップを目指したいと感じたときは、移行を検討する良いタイミングといえるでしょう。障がい者雇用からの移行を検討したいタイミングについて詳しく解説します。
障がいの症状が改善し、障がい者手帳の返還が必要になったとき
うつ病や発達障がいなどで障がい者手帳を取得して働いていた方が、症状の改善によって手帳を返還しなければならなくなることがあります。この場合、障がい者雇用枠で働き続けられなくなるため、一般雇用に移行する必要が出てきます。企業側も制度に基づき対応するため、早めに相談し、一般雇用として働き続けられるかを確認しておくことが大切です。
キャリアアップや収入増を具体的に目指したくなったとき
障がい者雇用では、業務内容が限定される場合や、評価制度が十分に整っていない場合があります。そのため「さらに責任ある仕事に挑戦したい」「収入を増やしたい」と考えたときに、一般雇用への移行を検討する人も少なくありません。一般雇用では成果に応じた評価や昇進のチャンスが得られやすく、自分の頑張りがキャリアや収入に直結しやすい環境が整っています。
正社員として働きたいとき
長期的に安定した働き方を目指す場合、正社員雇用を希望する方も多いでしょう。一般雇用の方が正社員登用の求人が多く、安定した収入や福利厚生を得られる可能性が高まります。なお、障がい者雇用から契約社員として働き始め、その後に正社員登用を目指す方法もありますが、確実に正社員を目指したい場合には、一般雇用への移行を前向きに考えることが大切です。
転職活動の進め方
障がい者雇用から一般雇用に移行したい場合、闇雲に求人へ応募するのではなく、段階を踏んで準備を進めることが成功への近道です。ここでは、転職活動の進め方を順を追って解説します。
ステップ1:自己分析で「強み」と「必要な配慮」を言語化する
まずは自分自身の障がいの特性を理解し、どのような支援や配慮が必要なのかを整理することが重要です。得意な業務や発揮できる強み、逆に苦手でサポートが必要な部分を明確にしておくことで、自分に合った職場を見つけやすくなります。
ステップ2:障がいを開示するかを決める(オープン・クローズ就労)
次に考えるべきは、障がいを開示して就職するかどうかです。障がいを開示する「オープン就労」では、必要な配慮を期待でき、就労移行支援事業所を利用していれば就職後も支援を受けられるメリットがあります。しかし、場合によっては採用を敬遠されるリスクもあります。
一方で、障がいを開示しない「クローズ就労」では応募できる求人の幅が広がりますが、配慮を求めることは難しいでしょう。
ステップ3:求人情報を探す
自己分析と就労スタイルの選択が済んだら、具体的に求人を探していきます。就労移行支援事業所やハローワークを活用するのが一般的です。それぞれの特徴を理解し、自分に合った情報源を選ぶことが大切です。就労移行支援事業所とハローワークの違いについて詳しく見ていきましょう。
就労移行支援事業所
就労移行支援事業所は、障がいのある方が一般企業で働けるよう、職業訓練や就職活動のサポートを行う機関です。パソコンスキルやコミュニケーション能力のトレーニングなど、実務に直結するスキルを学べるだけではなく、職場に定着するための支援も受けられます。個別のニーズに合わせたサポートが手厚いのが大きな特徴です。
ハローワーク
ハローワークでは、障がい者雇用と一般雇用の両方の求人を扱っています。職業相談や応募書類の書き方指導、職業訓練の紹介などを受けられる他、オープン就労・クローズ就労いずれの場合でもサポートが可能です。地域ごとの求人情報を幅広く提供している点も強みです。
ステップ4:応募書類の作成と面接対策を行う
応募する求人が決まったら、履歴書や職務経歴書といった応募書類を整えます。オープン就労を希望する場合は、障がい者手帳の写しが必要になることもあります。応募前に就労移行支援事業所やキャリアカウンセラーに書類をチェックしてもらうと安心です。また面接対策として模擬面接を受けたり、病状や配慮が必要な点をどう伝えるかを練習したりしておくと良いでしょう。体調管理を整え、安定して勤務できる準備をしておくことも大切です。
まとめ
障がい者雇用から一般雇用への移行は、キャリアアップや収入増といった大きなメリットがある一方で、サポート体制が弱まるなど注意点もあります。症状の改善やキャリアの希望など、自分の状況に応じたタイミングで移行を検討することが大切です。
転職を成功させるには、自己分析から求人探し、応募書類の作成、面接対策までのステップを丁寧に進めることが欠かせません。サポートを受けながら安心して転職活動を行いたい方は、就労移行支援事業所を活用するのがおすすめです。
ココルポートでは就労支援サービスに加えて「就労定着支援サービス」も提供しており、転職後に新しい職場へ定着するまでを継続的に支援しています。就職を考えている方はもちろん「働き始めてからもサポートがほしい」という方も、まずは気軽にご相談ください。
こんなお困りありませんか?
以下はよくご相談いただく課題やお悩みの例になります。
ご自身にあてはまる課題やお悩みをクリックするとご提案の例が表示されますのでぜひご参考にしていただければと思います。
チャレンジすることに不安があるかもしれませんが、Cocorportは「失敗できる場」なので、ぜひいろいろなことにチャレンジしていただければと思います。
-
自己分析(理解)
-
対人コミュニケーション
-
体力・生活リズムストレス耐性
-
職場定着・相談先
-
就職活動・スキル
関連記事
関連アイテムはまだありません。
- お電話はこちら
- 0120-336-866
※お電話受付時間 9:00~18:00(日曜定休)

お気軽にお問合せください!
開催予定の就労移行支援の説明会情報
-
大船Office
大船Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料) -
博多Office
Cocorport 博多Officeで就職活動をはじめませんか? -
Cocorport Rework 新横浜駅前
新横浜で、もう一度働きたいあなたへ。メンタル疾患からの復職を専門チームが支えます -
Cocorport Rework 横浜西口
横浜で、もう一度働きたいあなたへ。メンタル疾患からの復職を専門チームが支えます -
横浜戸塚Office
随時受付中✨横浜戸塚Officeに見学に来ませんか?見学会&相談会(参加無料) -
川越Office
Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料)※プログラム体験会も開催中 -
名古屋栄Office
Cocorport 名古屋栄Office見学会&就職個別相談会のお知らせ(参加無料) -
目黒駅前Office
Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料) -
所沢第3Office
Office見学会&就職個別相談会のお知らせ(参加無料) -
所沢Office
Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料)※プログラム体験会も開催中
Officeブログ新着情報
-
所沢第3Office 2026/02/06
プログラム紹介「ビジネス文書のルールとマナー」 -
登戸Office 2026/02/06
【登戸Office】グループワークでオリジナル人生ゲーム作成中🐣 -
新浦安駅前Office 2026/02/06
🧮模擬就労~残業状況集計~のご紹介🧮 -
立川駅前Office 2026/02/06
【トレイニーさんブログ】「HSP」について -
北千住Office 2026/02/06
【2月前半開催プログラム紹介】メリハリある時間管理術🕙 -
Cocorport Rework 大宮 2026/02/06
【トレイニーブログ】~認知行動療法でストレスをセルフケアする~ -
勝田台第2Office 2026/02/05
【Cocorport勝田台第2Office】スタッフ紹介~私の推し編~ -
赤羽Office 2026/02/05
【赤羽Office】ココルポートvoice 2月号のご紹介🫘 -
京都四条河原町駅前Office 2026/02/05
プログラム紹介:上手な力の抜き方 -
大阪なんば駅前Office 2026/02/05
⛄2月のプログラム紹介⛄