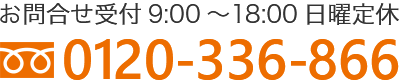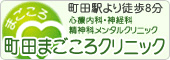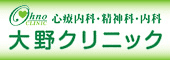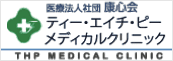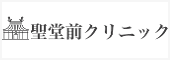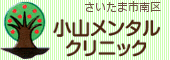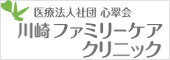- ココルポート(就労移行支援・定着支援/自立訓練/計画相談) HOME
- 就労移行支援とは
- 就労選択支援とは
就労選択支援とは?対象や利用料、サービス内容を丁寧に解説
ここでは、「就労選択支援」のイメージをもってもらうために全体の流れをわかりやすく、簡潔に説明します。
- 就労選択支援とは、障がいのある方が就労先・働き方を選ぶ際に、ご本人の希望や就労能力、適性等に合った選択を支援する新たなサービスです。
- 就労移行支援を利用するときには必須ではありませんが、就労継続支援B型を利用したいときは就労選択支援を原則受ける必要があります。
- ご本人からの情報を得るだけでなく、ご本人が進路選択の参考になるようなさまざまなサービスや働き方についての説明を行います。
- アセスメントシート(※)を活用し、ご本人の希望や情報を分かりやすく整理し今後のプランを一緒に考えていきます。
※ 障がいのある方の支援ニーズや就労能力の現状等を把握し、適切な支援につなげていくための評価ツール - アセスメントを整理して終わり、ではなく次の適切な支援の提供のために必要な連絡調整を行います。
就労選択支援って何?
障がいのある方が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、ご本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援する新たなサービスです。
→ 就労選択支援は自立訓練(生活訓練)/就労移行支援/就労定着支援といったサービスとは別の新しいサービスとなります。
就労選択支援サービスを受けられるところはどんなところなの?
就労選択支援サービスは、以下の事業所等でサービス提供を行っております。
※ 実施基準を満たす必要があるため、実施していない事業所等もあります。
- 就労移行支援事業所
- 就労継続支援事業所
- 障がい者就業・生活支援センター事業の受託法人
- 自治体設置の就労支援センター
- 障がい者能力開発助成金による障がい者職業能力開発訓練事業を行う機関
自立訓練では原則実施できません
就労選択支援サービスはどんな場合に受ける必要があるの?
- 令和7年(2025年)10月から就労継続支援B型を新たに利用したい方は原則対象となります。
- 令和9年(2027年)4月から就労継続支援A型を新たに利用したい方は原則対象となります。
- 就労移行支援を新たに利用したい方は必須ではありません。
| サービス類型 | 新たに利用する 意向がある障害者 |
既に利用しており、支給決定の 更新の意向がある障害者 |
|
|---|---|---|---|
| 就労継続支援B型 | 現行の就労アセスメント対象者(下記以外の者) | 令和7年10月から原則利用 | 希望に応じて利用 |
| ・ 50歳に達している者または障害基礎年金1級受給者 ・ 就労経験ありの者(就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった者) |
希望に応じて利用 | ||
| 就労継続支援A型 | 令和9年4月から原則利用 | ||
| 就労移行支援 | 希望に応じて利用 | 令和9年4月から原則利用 ※ 標準利用期間を超えて更新を希望する者 |
|
【引用】厚生労働省 就労選択支援実施マニュアル 5P
※ 就労アセスメント:働くために必要な能力や適性、希望、課題などを総合的に分析・評価すること

「就労選択支援」に置き換わるようなイメージとなります。
どんな障がいのある方が対象になるの?年齢制限などの条件は?
就労選択支援は、「障がい福祉サービス」のひとつです。そのため、「受給者証」を取得していることが基本的な条件となります。
障がい種別やその他の条件については以下をご確認ください。
<障がい種別について>
就労選択支援は、障がいの種類に関係なく、ご利用者様の希望や能力、適性に合わせて就労の選択肢を広げる支援を目的としています。そのため、特定の障がいが対象と明確に決まっているわけではありません。
※ 以下に記載したとおり
- 精神障がい、知的障がい、発達障がい、身体障がいなどの障がいのある方
- 障害者総合支援法の対象疾病となっている難病等のある方
<その他の条件>
就労経験があるかどうかは利用の条件にはなっていません。
そのため、特別支援学校の生徒の方などまだ就労経験のない在学中の方も利用可能です。
就労選択支援の利用料はどのくらい?
ご本人または配偶者の前年度所得に応じて、利用料(1割負担)がかかる場合があります。
詳しくは以下表をご確認ください。
| 区分 | 世帯収入状況 | 負担額/月 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 負担なし |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯(注1) | 負担なし |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)(注2) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム・ケアホーム利用者を除く(注3) |
9,300円/上限 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円/上限 |
(注1)3人世帯で障がい基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象となります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合「一般2」となります。
*その他の要件によって減免等がありますので、お住まいの行政担当課にお問い合わせください。
就労選択支援サービスを利用するにはどうすればよいの?利用できる期間は?
他サービスと同様、利用を希望する場合は計画相談事業所(またはセルフプラン)によりサービス等利用計画案が作成され、「就労選択支援」の受給者証が発行されます。
また、就労選択支援の支給決定期間は原則1か月です。この間でアセスメントから事業者との連絡調整までを一体的に行います。

【引用】厚生労働省 就労選択支援実施マニュアル 9P
就労選択支援サービスってどんなことをするの?
原則利用できる1カ月間の間で、以下に記載した項目を行います。
⓪ ご本人への情報提供等
① 作業場面等を活用した状況把握(アセスメント)
② 多機関連携によるケース会議
③ ご本人との協同によるアセスメントシートの作成
④ 事業者等との連絡調整
詳細については、それぞれの項目ごとに説明します。

【引用】厚生労働省 就労選択支援実施マニュアル 19P
⓪ ご本人への情報提供等
就労選択支援を何のために利用するのか、どのようなサービス内容か、本人がわかりやすく理解できるように情報提供を行います。
- 就労選択支援では何をやるのか?
- なぜ就労選択支援をやるのか?これに加えて…
- どのような障がい福祉サービスがあって何をしているか?(就労継続支援A型/就労継続支援B型/就労移行支援等)
- 他のサービスはどのようなものがあるか?(ハローワーク/職業リハビリテーション等)
- どのような働き方があるか?(一般就労/障がい者雇用等)

① 作業場面等を活用した状況把握(アセスメント)

面談
(本人/保護者/本人と保護者など)
模擬的就労場面
標準化検査
(GATBなど)
- ご本人との面談や訓練を通して、ご本人のニーズ・希望・適性やスキルを確認する。
- 実施期間の目安は1~2週間ほど。
② 多機関連携によるケース会議
ご本人を中心として、共有や今後の検討を行います。
- ご本人に関する基礎情報の共有
- ご本人の希望や考え
- 就労選択支援員としての所感の共有
- 考えられる今後の方向性
- 各機関の役割分担の確認

③ ご本人との協同によるアセスメントシートの作成
作業場面等による状況把握(アセスメント)などを基に得られた情報をシートに落とし込み、ご本人の情報をわかりやすく整理し、「就労に向けた今後のプラン」を考えていくために必要なものです。
就労における利用者の現状と課題について、 ご本人・ご家族、各関係機関に客観的に伝えるために有効です。
※ 障がいのある方の支援ニーズや就労能力の現状等を把握した適切な支援につなげていくための評価ツール
- ご本人の意見と就労支援の専門家(=就労選択支援員)の助言を織り交ぜて、ご本人や家族、関係機関にとって分かりやすい内容や表現を心がけます。
- 「就労の可否の判断」ではなく「就労に向けた今後のプラン」を考えるためのものです。

補足:特別支援学校在籍者の方に対する就労選択支援の実施について
また、在学中に複数回実施することや、職場実習のタイミングでの実施が可能です。

【引用】厚生労働省 就労選択支援実施マニュアル 6P
- お電話はこちら
- 0120-336-866
※お電話受付時間 9:00~18:00(日曜定休)

お気軽にお問合せください!
開催予定の就労移行支援の説明会情報
-
名古屋栄Office
Cocorport 名古屋栄Office見学会&就職個別相談会のお知らせ(参加無料) -
目黒駅前Office
Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料) -
所沢第3Office
Office見学会&就職個別相談会のお知らせ(参加無料) -
所沢Office
Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料)※プログラム体験会も開催中 -
Cocorport Rework 新横浜駅前
リワーク(復職支援)説明会&個別相談会(参加無料) -
Cocorport Rework 横浜西口
横浜で、もう一度働きたいあなたへ。メンタル疾患からの復職を専門チームが支えます -
所沢第2Office
Office見学会&就職個別相談会のお知らせ(参加無料) -
北朝霞Office
Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料)※プログラム体験会も開催中 -
朝霞台Office
Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料)※プログラム体験会も開催中 -
大船Office
大船Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料)
Officeブログ新着情報
-
府中駅前Office 2026/01/30
🍫2月のおすすめプログラム🍫 -
北千住Office 2026/01/30
就職者のご報告🌸 -
名古屋大曽根Office 2026/01/30
🎀🍫2月前半のプログラムスケジュール🍬🧣 -
センター北駅前Office 2026/01/30
📚✨本棚を新調しました📚✨ -
千葉Office 2026/01/30
【ご案内】参加無料☝🏻2月のオンライン講座📝 -
目黒駅前Office 2026/01/30
2月おすすめプログラムのご紹介🍀 -
横浜戸塚Office 2026/01/30
初詣に行ってきました! -
目黒駅前Office 2026/01/30
第2回🌹プログラム紹介【セルフマネジメント】 -
相模原橋本Office 2026/01/30
2月前半のおすすめプログラムのご紹介【相模原橋本Office】 -
京都四条河原町駅前Office 2026/01/30
余暇プログラム「はぁって言うゲーム♪」