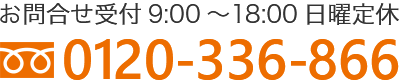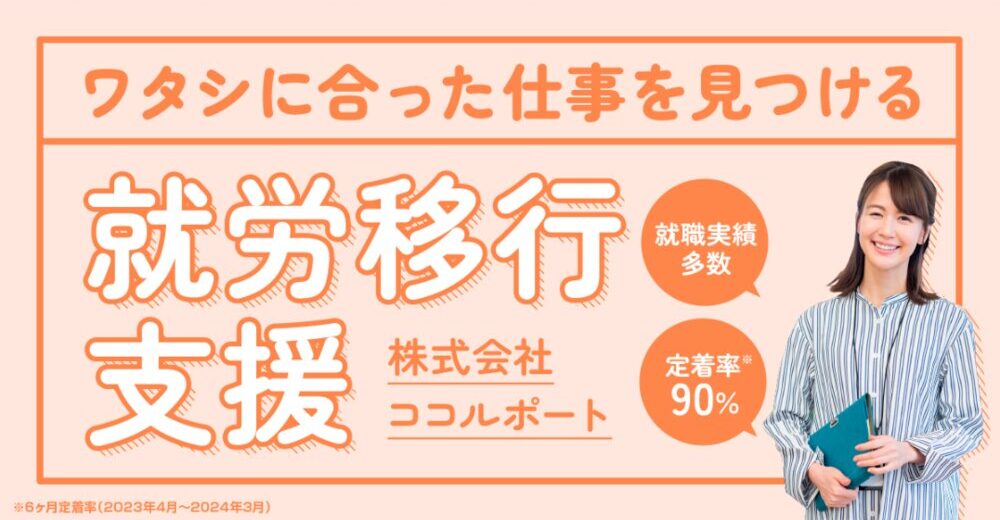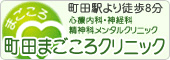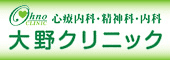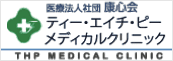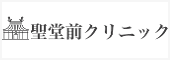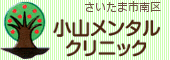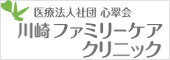- ココルポート(就労移行支援・定着支援/自立訓練/計画相談) HOME
- お役立ち情報
- うつ病再発のサインは? 原因や対策を解説
うつ病再発のサインは? 原因や対策を解説
公開日:2025/05/12
更新日:2025/05/12

うつ病は、適切な治療によって回復が見込める疾患ですが、一度回復した後も再発する可能性があることが知られています。
中には、完治したように見えても数年経ってから再び症状が現れるケースもあります。再発を防ぐためには、「どのような場面で再発しやすいのか」「どのようなサインが現れるのか」「どのような対策が有効なのか」を正しく理解しておくことが大切です。
本記事では、うつ病の再発確率や主な原因、初期に現れやすいサイン、再発を防ぐための生活や仕事上の対策まで詳しく解説します。
目次
うつ病再発の確率はどのくらい?

うつ病は、治ったように見えても、再び症状が現れることが少なくありません。厚生労働省の資料によると、うつ病の再発率は約60%で、うつ病を2回経験した人では約70%、3回以上では約90%が再発するという報告もあり、再発を防ぐことの難しさが浮き彫りになっています(※)。
このような再発の背景には、症状が一見改善していても、内面に疲労感や気分の落ち込みと、あるいは不眠といった「残遺症状」が残っていることが関係しています。自分でも気づかないうちに無理を重ねたり、再び強いストレスにさらされたりすると、こうした症状が再燃する引き金になり得ます。
また、うつ病は年齢や性別、職業に関係なく誰にでも起こりうる病気です。日本では約15人に1人が生涯のうちにうつ病を経験するとされており、決して特別な人だけがなるものではありません。だからこそ、うつ病を「一時的な不調」と軽く見るのではなく、早期に発見し、長期にわたるケアを受けることが必要です。
※出典:厚生労働省「うつ病対応マニュアル-保健医療従事者のために」
うつ病の再発原因として考えられること

うつ病は一度回復しても、時間が経ってから再び症状が現れることが珍しくありません。その原因は解明されているわけではなく、さまざまな要因が複雑に絡み合っていると考えられています。
うつ病の再発を引き起こすとされる要因について紹介します。
生活環境・季節の変化
引っ越しや転職、進学など、新たな環境に身を置くと、知らず知らずのうちに心や体へ大きな負担がかかります。新生活は新鮮で前向きな印象がありますが、慣れない人間関係や生活リズムの変化は、強いストレス源となり得ます。
また季節の移り変わりも再発の要因です。たとえば日照時間が短くなる秋や冬には、脳内のセロトニンのはたらきが季節によって影響を受けることで、気分の落ち込みや睡眠リズムの乱れが生じやすくなります。最近では、夏の猛暑や長続きする残暑、気温の乱高下も、心身の調子に影響を与えている可能性があります。
病気の発症
糖尿病やがん、心筋梗塞など、体の大きな病気を経験することも、うつ病の再発リスクを高める重要な要因です。病気そのもののショックや、長期的な治療・療養生活による孤独や不安は、精神的な負荷として蓄積されていきます。
さらに、こうした病気はうつ病と合併しやすいこともわかっており、体の不調と心の不調が連動して悪化していくケースが少なくありません。体をいたわると同時に、心のケアにも目を向けることが、再発防止につながります。
感情の大きな変化
うつ病は、必ずしも「つらい出来事」だけで再発するわけではありません。結婚や出産、昇進など、一般的には喜ばしいとされる出来事であっても、その裏にプレッシャーや責任感が潜んでいることがあります。
新たな立場への期待と不安が入り混じる中で、心が疲弊してしまう人は少なくありません。また離婚や死別などの悲しみは、想像以上に心を揺さぶります。時間の経過とともに感情が落ち着くこともありますが、深い悲しみが長く続く場合には、うつ病の再発リスクが高まります。
自己判断による治療の中断
うつ病の治療によって症状が少しずつ改善してきた際に「もう大丈夫」と感じ、自己判断で薬の服用をやめたり、通院をやめたりすると、脳内の神経伝達物質のバランスが整いきらないことで、再発しやすくなります。
うつ病の再発サイン
うつ病は一度治療によって改善しても、時間の経過とともに再び症状が現れることがあります。その際、早い段階で再発のサインに気づくことができれば、悪化を防ぎ、再び適切な治療につなげることが可能です。
再発のサインには、身体的な変化と精神的な変化の両方があり、日常生活の中で「なんとなく調子が悪い」と感じたときこそ注意が必要です。ここでは、うつ病の再発時に現れやすい兆候を、身体面と精神面に分けて紹介します。
身体面
うつ病の再発の兆候として、次のようなサインが現れることがあります。
- ・寝つきが悪くなる、夜中に目が覚める、早朝に目が覚めてしまうなどの睡眠の乱れが見られる
- ・しっかり休んでも疲れが取れず、常に体が重く感じる
- ・急に食欲が増すなど、食習慣に明らかな変化が出る
- ・明確な病気がないのに、頭痛・めまい・吐き気などの体調不良が続く など
単なる体調不良と判断されやすいものですが、心の不調が背景にあるケースも多くあります。
精神面
再発の兆候は心にも現れます。気分の変化や思考パターン、感情の扱い方に異変が見られた場合は、再発の可能性を考えることが大切です。主な兆候は下記の通りです。
- ・気分が晴れず、理由もなく落ち込みがちになる
- ・物事を悲観的に考えてしまい、前向きになれない
- ・何をするにも気力が湧かず、行動するのが億劫になる
- ・イライラしたり涙が出たりと、感情のコントロールが難しくなる など
気分が落ち込むだけではなく、「楽しいと思えることが楽しめない」「将来に対して極端に悲観的になる」といった変化も見逃せません。
うつ病の再発対策
うつ病の再発を防ぐためには、日々の生活や治療との向き合い方に注意を払うことが大切です。一度改善したとしても、環境の変化やちょっとした無理が再発の引き金になることもあります。ここでは、うつ病を再発させないために意識したい4つの対策について紹介します。
継続した服薬
うつ病の治療で基本となるのが薬物療法です。抗うつ薬は脳内の神経伝達物質のバランスを整える役割を持ちますが、効果を実感できるようになるまでには時間がかかります。また、症状が落ち着いたと感じたときほど自己判断で服薬をやめたくなるものですが、それはリスクの高い行為です。
再発を防ぐために、医師の指示に従って継続的に薬を服用し、自己判断で薬の量を変えたり中断したりしないようにしましょう。不安であれば、いつまで薬を飲んだらいいのか、医師と相談する機会を持つのがおすすめです。
規則正しい生活リズム
心の安定は、体のリズムと密接に関係しています。不規則な生活や睡眠不足、食生活の乱れは、自律神経やホルモンバランスを崩し、うつ病再発のリスクを高めます。
朝起きて日光を浴びる、適切なタイミングで食事を取る、軽い運動をするなど、生活の基本を整えることは、心身の回復にもつながります。日々の生活の中に“自分を整える習慣”を意識的に取り入れましょう。
体を休めてリフレッシュ
再発を防ぐ上で、心と体を休ませる時間をきちんと取ることも大切です。仕事や家事などの役割に追われ続けていると、自分を見つめ直す余裕がなくなり、ストレスも気づかないうちに蓄積されていきます。
短時間でも趣味を楽しんだり自然と触れ合ったりして、自分自身のリズムを取り戻すようにしましょう。
カウンセリングの利用
身近に話せる相手がいない、またはうまく気持ちを伝えられないという場合には、専門のカウンセラーを頼ることも方法の一つです。カウンセリングでは、心の中にたまった思いや不安を整理する手助けをしてくれます。
感情を吐き出すだけでも気持ちが軽くなり、再発の予防や早期対応にもつながるはずです。一人で頑張り過ぎず、外部のサポートを積極的に活用しましょう。カウンセリングは一般的に保険診療でカバーされず、経済的な負担がかかるため、間隔や期間を決めて行うのも一つの方法です。
仕事でうつ病の再発対策をするには?
うつ病の再発を防ぐには、日常生活でのケアに加えて、仕事の場での対策も重要です。仕事は生活の大きな一部であり、心身にかかる負担も小さくありません。
適切な支援を受けながら無理のない働き方を実現することが、再発リスクを下げ、安定した社会生活を続ける鍵になります。ここでは、職場での再発防止に役立つ取り組みについて紹介します。
休職して治療に専念
再発の兆候が強く現れた場合、思い切って休職を選択することも大切な判断です。仕事を続けながら治療を続けることが難しいと感じたときは、無理をせず、主治医と相談の上で休職を前向きに検討しましょう。
休職によって精神的・身体的な負荷を減らすことができ、結果的に早期回復や再発防止にもつながります。
業務の合理的配慮を相談
再発を避けるためには、職場の環境や業務内容について見直すことも効果的です。令和6年(2024年)4月1日から義務化された「障がいのある方への合理的配慮」は、企業が無理のない範囲で業務を調整する仕組みで、うつ病の方にも適用されます。
職場の上司や人事担当者と話し合いながら、自分にとって必要な配慮を一緒に検討していきましょう。
障がい者の支援機関を利用
仕事と病気の両立に悩んでいる方は、外部の支援機関を利用するのも方法の一つです。就労移行支援事業所や地域障がい者職業センター、障がい者就業・生活支援センターなどでは、仕事選びから職場定着まで幅広いサポートを受けることができます。
一人で抱え込まず、支援を受けながら自分に合った働き方を見つけましょう。
リワークを利用
うつ病などで休職した方が、職場復帰に向けて段階的に準備を進める「リワークプログラム」も再発対策として効果的です。主治医の判断や本人の希望を元に、模擬業務やストレス対処訓練などを通じて、復職に必要な力を整えていきます。自信を持って職場に戻るためのステップとして、ぜひ活用を検討してみてください。
障がい者雇用の求人を探す
うつ病を繰り返すことで、一般的な働き方に不安を感じている方には、障がい者雇用枠での就労を検討してみてください。障がいに理解のある職場環境が整っていることが多く、自分のペースで働きやすい点が特徴です。
精神障者がい保健福祉手帳を取得することで応募可能な求人も増えるため、今後の働き方を見直す上で検討する価値があります。
うつ病は精神障がい者保健福祉手帳の取得対象疾患ですが、手帳は初診してすぐに申請できるわけではなく、初診日から6カ月以上経過していなければなりません。したがって、治療に難渋している、回復が思わしくないあるいは病前の状態に戻ることが難しい場合などに、検討される場合が多くなります。
まとめ
うつ病の再発は、誰にでも起こり得ます。再発率は決して低くはなく、油断や無理が引き金となって再び症状が現れることもあります。ただし、体や心の小さなサインを見逃さず、早期に気づいて適切な対応を取ることで、再発を抑えることは可能です。
しかしながら、「一人で対策を続けていくのは不安」「働きながらうまく付き合っていけるか心配」という方もいるでしょう。
ココルポートは徹底的な個別支援にこだわり、うつ病などの精神的な不安がある方の就労や自立をサポートしています。就職はゴールではなく、その先の人生をより自分らしく歩んでいくための手段だからこそ、一人ひとりの状況や目標に合わせた柔軟な支援を大切にしています。
週1〜2回の通所からスタートした方が、少しずつステップを重ねて就職・定着へとつながるケースも多数あります。2023年度には762名が就職し、定着率は90%に達しています。
うつ病の再発を懸念されている方も、まずはお気軽にご相談ください。
監修者プロフィール
こんなお困りありませんか?
以下はよくご相談いただく課題やお悩みの例になります。
ご自身にあてはまる課題やお悩みをクリックするとご提案の例が表示されますのでぜひご参考にしていただければと思います。
チャレンジすることに不安があるかもしれませんが、Cocorportは「失敗できる場」なので、ぜひいろいろなことにチャレンジしていただければと思います。
-
自己分析(理解)
-
対人コミュニケーション
-
体力・生活リズムストレス耐性
-
職場定着・相談先
-
就職活動・スキル
- お電話はこちら
- 0120-336-866
※お電話受付時間 9:00~18:00(日曜定休)

お気軽にお問合せください!
開催予定の就労移行支援の説明会情報
-
名古屋藤が丘駅前Office
Cocorport 名古屋藤が丘駅前Office見学会&就職個別相談会のお知らせ(参加無料) -
大船Office
大船Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料) -
川越第2Office
Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料)※プログラム体験会も開催中 -
目黒駅前Office
Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料) -
Cocorport Rework 大阪天王寺駅前
リワーク(復職支援)現地説明会&オンライン説明会(参加無料) -
Cocorport Rework 藤沢
リワーク(復職支援)現地説明会&オンライン説明会(参加無料) -
川越第3Office
Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料)※プログラム体験会も開催中 -
名古屋大曽根Office
Cocorport 名古屋大曽根Office Office見学会&就職個別相談会のお知らせ(参加無料) -
名古屋駅Office
Cocorport 名古屋駅Office Office見学会&就職個別相談会のお知らせ(参加無料) -
Cocorport Rework 松戸駅前
リワーク(復職支援)説明会&個別相談会(参加無料)
Officeブログ新着情報
-
北千住Office 2026/02/27
【プログラム内容&感想】花結びチャームづくり🌷 -
Cocorport Rework 大阪天王寺駅前 2026/02/27
スタッフ紹介⑤ -
横浜戸塚Office 2026/02/27
企業見学のポイント☆彡 -
横須賀第2Office 2026/02/27
横須賀第2Office 環境整備部 始動! -
新板橋駅前Office 2026/02/27
プログラム紹介【自己PRの作成】 -
新板橋駅前Office 2026/02/27
プログラム紹介【今日からできる時間管理術】 -
新板橋駅前Office 2026/02/27
プログラム紹介【メモ取り基本編】 -
名古屋藤が丘駅前Office 2026/02/27
🍑3月前半プログラム紹介🍑 -
南浦和駅前Office 2026/02/27
ココルポートでできること🪄 -
長津田駅前Office 2026/02/26
プログラム紹介 余暇「格付けチェック!!」