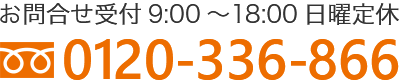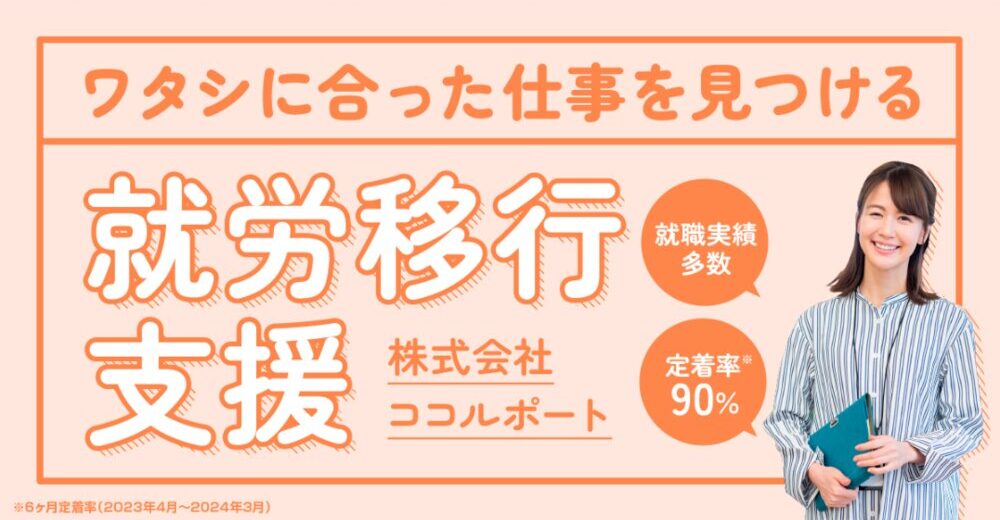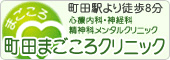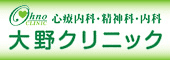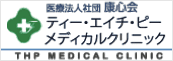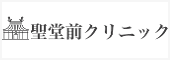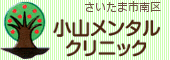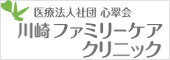- ココルポート(就労移行支援・定着支援/自立訓練/計画相談) HOME
- お役立ち情報
- 不安症(不安障がい)で仕事に行くのが怖い? 5つのポイントをご紹介
不安症(不安障がい)で仕事に行くのが怖い? 5つのポイントをご紹介
公開日:2022/04/21
更新日:2025/04/24

不安症のある方の中には、
「不安症がありながら、本当に働けるのだろうか」
「仕事中に強い不安に襲われたらどうしよう」
など、仕事に就くことへの不安があるかもしれません。
しかし、不安症の特性を理解し上手に付き合うことができれば仕事を続けていくことも可能です。大事なことは一人で不安や恐怖を抱え込まないことです。
本記事では、不安症のある方が仕事をするための具体的な方法や頼れる社会資源について解説していきます。
※近年の世界保健機関(WHO)などの診断基準の改訂により、「不安障がい」は「不安症」という名称へ移行しつつあります。ここでは、「不安症」に統一してお話を進めます。
目次
不安症(不安障がい)とは
不安症(不安障がい)とは、日常生活において過度の不安を感じ、生活に影響を及ぼす精神疾患です。不安症は様々な形で表れ、それぞれに特徴的な症状があります。
アメリカ精神医学会の「DSM-5-TR(精神疾患の診断・統計マニュアル:第5版 Text Revision)」では、不安症群として「パニック症」や「広場恐怖症」などが記載されています。
「パニック症」は、突然の強い不安感や恐怖感を伴う発作が特徴で、動悸や呼吸困難、めまいなどの身体的な症状が表れます。「広場恐怖症」は、公共交通機関を利用している時や広いあるいは囲まれた場所にいる時に強い不安感を覚える症状です。
症状の程度は人によって異なり、その影響も多岐にわたりますが、適切な治療とケアにより改善が見込まれます。
参照:厚生労働省「不安障害」
不安症(不安障がい)の特性がありながら仕事をしている方の声
ここでは、不安症の特性がありながら仕事をしている方々を対象に行ったアンケートデータを基に、具体的な体験談を紹介します。
- ・不安症(不安障がい)の方はどんな雇用形態で働いている?
- ・不安症(不安障がい)の方はどんな仕事をしている?
- ・不安症(不安障がい)の方が仕事を決める際に気をつけたこと
- ・不安症(不安障がい)の方が仕事で困ったこと
【アンケート概要】
調査時期:2023年7月5日~2023年7月6日
回答数:100件
調査手法:インターネット調査
調査対象:不安症(不安障がい)の特性を持ちながら仕事をしている方
調査実施:インターネットリサーチ会社
不安症(不安障がい)の方はどのような職種で働いている?
不安症の特性がありながらも、様々な職場で力を発揮している方は多いです。以下、アンケート結果を基にグラフを作成しました。
▼現在の職種を教えてくだい

グラフを見ると、一般社員として会社に勤めている方が最も多く、次いでパート・アルバイト、フリーランスとして働いている方が多いのが分かります。
具体的な職業としては、一般事務、小売業、製造業、飲食店、フリーライターなどが見受けられました。
不安症を抱えていても職場の理解とサポートがあれば、様々な職業で働くことが可能です。
不安症(不安障がい)のある方はどんな仕事をしている?
不安症のある方も、様々な職業で活躍しています。具体的な仕事内容は、以下の通りです。
| 職業 | 仕事内容 |
|---|---|
| 事務員 | データ入力、書類作成、経理、受付、電話対応等 |
| ホテル・飲食スタッフ | ホテルのフロント対応、お客様の食事対応等 |
| 建設・土木作業員 | 土木作業、現場まで重機を運ぶ等 |
| コンビニ店員 | レジ打ち、品出し作業等 |
| 介護職員・生活支援員 | 障がい者に対する生活・就業のサポート等 |
| フリーランス※ | 韓国語講師、造園、建築物の設計、webライター、デザイナー等 |
※自営業・個人事業主含む
不安症(不安障がい)のある方が仕事を決める際に気をつけたこと
不安症のある方が仕事を決める際、特に気をつけたこととして、以下のようなことが挙げられました。
- ・ストレスがあまりなさそうな職場を選んだ
- ・人との関わりが少ない仕事を選んだ
- ・シフトの融通はききそうか、またワンオペ業務はないか
- ・勤務時間が固定されていて、休日が多い職場を選んだ
- ・家から通勤距離が短く、何かあったらすぐに帰れるか
慎重に仕事を決めれば、自分の体調やストレス管理をしながら、1つの職場で働き続けることができるかもしれません。
不安症(不安障がい)の方が仕事で困ったこと
不安症のある方が仕事で困ったこととして、アンケートから得られた声を紹介します。
- ・自分が責任者となる役職や業務に抵抗を感じて困った
- ・その日の精神状態や体調により、コミュニケーションに支障が出ること
- ・お客様の前で料理を提供する時に手が震えること
- ・会議や講習などで、狭い空間に人がたくさん集まると具合が悪くなる
上記の他にも「仕事が増えると不安になる」「電話応対は不安と緊張が強くなる」といった声が多く見受けられました。
不安症(不安障がい)の方の仕事上での困りごと
不安症のある方の困りごとの中で共通しているのが、不安や恐怖に伴う突然の発作が日常生活の中で起こることです。ここでは代表的な5つについてご紹介します。
- ・人前で話すことが怖い
- ・電話対応が怖い
- ・人が多く集まる場所に行けなくなる
- ・電車やバスに乗りにくくなる
- ・不安から仕事に行けなくなる
それぞれ詳しく解説します。
人前で話すことが怖い
不安症の中でも「社交不安症」で典型的にみられる症状ですが、会議での発言やプレゼンテーションなど人前で話す時に強い不安や緊張に襲われたり、人によっては過呼吸や動悸といった身体症状が表れたりすることがあります。
また、上記の経験を繰り返すことで、人前で話すことに対し恐怖を感じるようになる方もいます。
電話対応が怖い
職場の人の前で電話対応することに対し過度に緊張し、声が震えたりうまく話せなくなったりします。「電話恐怖」といわれることもあります。
また、電話の相手に「変な人」と思われないか心配するあまり、過度に緊張してしまうこともあります。
人が多く集まる場所に行けなくなる
人前に出たり話したりすることに不安や緊張があることから、人が集まる場所自体に恐怖を感じることがあります。
また、人前で発言したが緊張してうまくできなかったなどの経験があると、「またそうなってしまうのではないか」という予期不安を抱くことがあります。すると、会議に出られないなど人が多く集まる場所自体を避けようとします。
電車やバスに乗りにくくなる
広場恐怖症やパニック症がある場合、急な発作や体調不良に襲われた際に逃げることができないという状況や、助けを得にくい状況への強い心配・恐怖から、電車やバスに乗ることが難しくなります。
不安から仕事に行けなくなる
不安症の症状のために職場でうまく行動できなかった経験があると、「次もまた同じ症状が出たらどうしよう」と予期不安が生まれることがあります。すると、その予期不安が生じる可能性がある場所や機会を避けようとしてしまいます。
そのため、結果的に電車やバスに乗れない、仕事に行けなくなる、という状況になります。
また、このように特定の状況を回避する状態が続くと、苦手な状況を克服する「成功体験」を持つ機会も失われてしまいます。その結果、さらに不安が強くなってしまい、現状から抜け出せない悪循環に陥ってしまう可能性もあります。
不安症(不安障がい)の方が仕事を継続するための5つのポイント
不安症の方が仕事を継続するためのポイントには、生活リズムを整える、不安が生じた時の対策を考えておくなどがあります。具体的に解説していきます。
- ・食生活・生活習慣を整える
- ・服薬を継続する
- ・不安が強くなった時の対処方法を決めておく
- ・周囲の人の理解を得る
- ・休む勇気を持つ
それぞれ詳しく見ていきましょう。
食生活・生活習慣を整える
食事や睡眠などの生活リズムが乱れると、心身のバランスを崩しやすくなります。栄養バランスの良い食事、適度な運動、十分な睡眠などを心掛けることは不安や恐怖への心の抵抗力をつけることにもつながります。
カフェイン(コーヒー、紅茶、お茶など)やアルコールは不安を強めることがあるため、とりすぎには注意しましょう。
服薬を継続する
不安症に対して主に用いられる薬(いわゆるSSRIと呼ばれるもの)は、飲み続けることで治療や予防の効果が表れます。
調子が良い状態が続いたり忙しくなったりすると、つい薬を服用することを忘れることがありますが、主治医から指示がある際は服薬を継続することが望ましいです。
もし疑問がある時や薬をやめたいと思った時は、医師に相談することが大切です。
不安が強くなった時の対処方法を決めておく
自分がどういう時に不安や恐怖を感じやすいのかを理解し、それに合わせた対処方法や工夫を考え実践することが大切です。呼吸法や筋弛緩法、タッピングなどがよく用いられるものの一例です。
あらかじめ対応策を考えておくことで、不安や恐怖を感じても適切に対応でき、それが成功体験につながり、過度に活動を抑制することなく日常生活を過ごすことにもつながります。
周囲の人の理解を得る
不安症の方が継続して働くためには、自分の努力だけでなく周囲の理解や困った時にサポートを受けられるような環境を作っておくことが大切です。
不安症の特性や自身の傾向を伝えておくことで、仕事内容の配慮や支援をしてもらえる可能性もあります。
休む勇気を持つ
心身ともに調子がすぐれない時は、我慢をせずに休むことも考えてみましょう。
休むことにも勇気がいるかもしれませんが、状態が悪化するほど回復にも時間がかかってしまいます。
長く安定して仕事を続けるためにも、調子が悪い時は休むという選択をすることも大切です。
不安症(不安障がい)の方が続けやすい仕事
不安症の方が続けやすい仕事の特徴を3つ解説していきます。
- ・対人関係が少ない仕事
- ・業務にむらがない定型的な仕事
- ・在宅勤務が可能な仕事
それぞれ詳しく解説します。
対人関係が少ない仕事
常に人と接する仕事は、緊張感から不安を抱きやすくなりストレスとなります。
共同作業ができるだけ少ないほうが、対人ストレスの機会を減らすことができ、自分の体調に合わせて仕事をコントロールしやすいことから、仕事の続けやすさにつながる場合があります。
業務にむらがない定型的な仕事
業務量や内容が変化しやすい仕事は、その都度臨機応変な対応が求められ不安も強くなりやすいです。
可能であれば、業務量や内容が大きく変わらず、見通しを立てやすい仕事を選ぶことで、不安を軽減させられるかもしれません。
在宅勤務が可能な仕事
電車やバスに乗ることが難しかったり、人が多くいる環境にいるだけで不安や緊張が強くなったりする場合は、在宅でできる仕事を選ぶことも良いでしょう。
不安症(不安障がい)の方が避けたほうがいい仕事
不安症の方が就労について考える際、以下のような仕事を避けないと症状を悪化させる可能性があるため注意が必要です。
- ・勤務地や勤務時間が不規則な仕事
- ・責任感や圧力を感じやすい仕事
- ・社交性やプレゼン力が求められる仕事
それぞれ詳しく解説します。
勤務地や勤務時間が不規則な仕事
勤務地が頻繁に変わる仕事は、新たな環境に移るたびにストレスが発生します。環境の変動は不安を引き起こしやすいため、営業職やシステムエンジニアなど、出張や転勤が多い職業は可能な限り避けるべきです。
また、勤務時間が不規則な仕事は生活リズムも不規則になりやすく、健康に悪影響を及ぼす可能性があります。
たとえば、ホテルのスタッフや介護士、看護師のような夜勤や交代制の勤務では、生活リズムの乱れと睡眠の質の低下が生じやすいです。
責任感や圧力を感じやすい仕事
重大な責任が伴う仕事や高圧的な人がいる職場環境は、不安を誘発しやすい傾向にあります。
たとえば、看護師などの医療関係者は、他人の命を預かる重要な責任を伴います。このような仕事では、患者の健康に直接影響を与えるような業務がある可能性があります。そのため、不安を抱くことも多いでしょう。
また、厳しいノルマが課せられる営業職も同様に、ストレスが溜まりやすい仕事といえます。目標達成へのプレッシャーは精神的負担を生み、不安を増幅させる要因となるため避けたほうがよいでしょう。
社交性やプレゼン力が求められる仕事
営業職やコンサルタントのような仕事は、不安症の方にとってストレスになりやすいです。たとえば、営業や接客業など、頻繁に人との交流を求められる職業は、不安や緊張を感じやすい方には難しいかもしれません。
また、公の場で話す機会が多い職業も同様です。人前で話すのが苦手な方は、大勢の人々の前で発言したりプレゼンテーションを行ったりするシーンで、不安を感じることが多いです。
個々の症状や特性にもよりますが、これらの職業は避けるべきでしょう。
不安症(不安障がい)の方が仕事をする上で活用できる社会資源
経済的支援や仕事を探し継続していくためのそれぞれの段階に応じて活用できる社会資源を解説していきます。
経済的支援を受けられる社会資源
ここでは経済的支援を受けられる4つの資源を解説します。
- ・自立支援医療制度(精神通院医療制度)
- ・精神障がい者保健福祉手帳
- ・障がい年金
- ・傷病手当金
それぞれ詳しく見ていきましょう。
■自立支援医療制度(精神通院医療制度)
精神科の治療のために継続的に通院している方の医療費の自己負担額の一部を補助してもらえる制度です。
不安症の場合でも、計画的・集中的な治療を継続する必要がある(いわゆる「重度かつ継続」)と認められた場合は、同制度の適応となることがあります。
疾患や所得に応じて1カ月の自己負担上限額が設定されていますが、おおよそ医療費の1割程度の自己負担になる場合が多いです。
■精神障がい者保健福祉手帳
不安症の方の中には精神障がい者保健福祉手帳を取得できる場合があるので、一度主治医に相談してみましょう。
手帳の取得には、初めての受診日(初診日)から6カ月以上経過していることが条件の1つです。
精神障がい者保健福祉手帳を取得すると、疾患や程度に応じて様々な福祉サービスや公共施設利用料の割引などを受けることができます。
また「障がい者雇用」という枠で、障がいに対する理解や支援を得られやすい職場で働くこともできます。
■障がい年金
病気やけがによって生活や仕事に支障が出た時に受け取ることができる年金です。働いている場合でも、症状により仕事が制限されていると判断された場合は、生活の一部を支援する金額が支給されます。不安症は原則対象外ですが、症状によっては申請できることもあるため主治医や社労士へまずは相談してみましょう。
■傷病手当金
健康保険に加入している場合に、病気やけがのために働くことができず長期間休職した時に、生活を保障する目的で支給される手当金です。
傷病によって3日連続して休んだ後の4日目以降の休みから給付の適応となり、医師の診断書が必要となります。
仕事探しをする前の準備として活用できる社会資源
自分に合った仕事を探すための準備として活用できる2つの資源を解説します。
- ・就労移行支援事務所
- ・障がい者就業・生活支援センター
それぞれ詳しく見ていきましょう。
■就労移行支援事務所
障害者総合支援法に基づいて障がいのある方の社会参加をサポートするための福祉サービスです。
障がいのある方が一般企業への就労を目指すために「職業訓練の提供」と「就職活動の支援」によってサポートをしています。
■障がい者就業・生活支援センター
障がいのある方の暮らしや仕事についての総合的な支援を行っており、就職に関することや職場では話しづらい仕事上の悩み、健康問題などについて相談することができます。
仕事を探す時に活用できる社会資源
実際に仕事を探し始める時に活用できる2つの資源を解説します。
- ・ハローワーク
- ・就労移行支援事務所
それぞれ詳しく見ていきましょう。
■ハローワーク
就職や転職を目指す人々に対し職業紹介や求職相談、雇用保険の手続きといった支援を行います。
また障がいのある方の就労を支援する窓口「専門援助部門」があり、就職に関する相談やカウンセリングの実施の他、障がいや疾患のある方を対象にした求人の紹介などを行っています。
■就労移行支援事務所
障がいのある方が一般企業への就労を目指すために「職業訓練の提供」と「就職活動の支援」によってサポートをしており、面接の対策や履歴書の書き方なども支援してくれます。
また不安症の特性や本人が抱える悩みをよく理解した上で、働きやすい職場を探すお手伝いをしてくれます。
不安症(不安障がい)の方の仕事に関する悩みはココルポートへ
不安症は治療や生活習慣の工夫により改善が期待でき、症状が和らげば仕事で活躍することも可能です。不安症の症状による負担や不安軽減のために適切に社会資源を利用していきましょう。
就労支援の「ココルポート」は、不安症の方が就職や自立に向けて様々なスキルを身につけながら自分と向き合うことをサポートいたします。
「ココルポート」の特徴は「個別支援」に力を入れていることです。体調・悩み・希望を支援員に相談できる体制があります。また、就労へ向けたスキルはもちろん、セルフケアを身につけるサポートなど、様々な側面から就労の準備を一緒に整えていきます。
まずは「ココルポートの見学・相談」から気軽にお問い合わせください。
※ココルポートの実績
Cocorport(就労移行支援・定着支援)の就職実績及び定着実績について | 障がい者就労移行支援のCocorport
こんなお困りありませんか?
以下はよくご相談いただく課題やお悩みの例になります。
ご自身にあてはまる課題やお悩みをクリックするとご提案の例が表示されますのでぜひご参考にしていただければと思います。
チャレンジすることに不安があるかもしれませんが、Cocorportは「失敗できる場」なので、ぜひいろいろなことにチャレンジしていただければと思います。
-
自己分析(理解)
-
対人コミュニケーション
-
体力・生活リズムストレス耐性
-
職場定着・相談先
-
就職活動・スキル
- お電話はこちら
- 0120-336-866
※お電話受付時間 9:00~18:00(日曜定休)

お気軽にお問合せください!
開催予定の就労移行支援の説明会情報
-
所沢第3Office
Office見学会&就職個別相談会のお知らせ(参加無料) -
所沢第2Office
Office見学会&就職個別相談会のお知らせ(参加無料) -
所沢Office
Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料)※プログラム体験会も開催中 -
川越Office
Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料)※プログラム体験会も開催中 -
高槻駅前Office
個別相談会・就職相談会情報 -
博多Office
Cocorport 博多Officeで就職活動をはじめませんか? -
日暮里Office
🌸🌸🌸日暮里office🌸🌸🌸事業所説明&見学について!! -
川越第3Office
Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料)※プログラム体験会も開催中 -
目黒駅前Office
Office見学会&個別相談会のお知らせ(参加無料) -
名古屋栄Office
Cocorport 名古屋栄Office見学会&就職個別相談会のお知らせ(参加無料)
Officeブログ新着情報
-
名古屋大曽根Office 2025/07/14
⚓🐬7月後半のプログラムスケジュール⛵🛟 -
三鷹駅前Office 2025/07/14
ココルポート三鷹駅前Officeトレイニーブログ文月号 -
横浜Office 2025/07/14
【オンライン 運動プログラム】ほぐして、伸ばして、鍛える 腰痛改善!ストレッチ&セルフマッサージ -
日暮里Office 2025/07/14
就職後もぜひ🌟【暑さ対策】ご紹介😊 -
流山おおたかの森駅前Office 2025/07/14
企業実習体験談!💡 -
目黒駅前Office 2025/07/14
【無料サービス】あったか昼食提供🍛✨ -
横浜関内Office 2025/07/14
知っておくと便利!私生活で使えるコミュニケーション -
朝霞台Office 2025/07/14
【朝霞エリア】オフィス内企業実習「TRY WORK」に参加しました -
武蔵浦和Office 2025/07/14
✨スタッフ紹介第1弾!✨ -
Cocorport Rework 船橋 2025/07/11
復職者インタビュー🎤✨